四時になるのは案外あっという間だった。
「ごめんなさい。遅くなりました」
さっき会った時は、警戒していたとはいえ、随分ぞんざいな口のきき方をしていたと思い、僕は口調を改めた。が、葵さんが「さっきみたいに話してくれた方が、気が楽」と微笑むので、普段通りの口調で話すことになった。
「親御さん達、心配しない? 大丈夫?」
などと心配してくるあたり、この人は常識人なのだろう。聞けば、彼女は六年前に柚葉小学校を卒業した高校生ということだった。てっきり、もっと年上かと思っていたのだけど、近所のお兄ちゃん達とさほど差がないようですぐに葵さんと打ち解けられた。
学校まではそう遠くないけれど、その短い時間の間に気付けばいろんな話をするほど親しくなっていた。
「そういえば、葵さん、もしかして一人で行くつもりだったの?」
何気ない疑問を口にする。すると、葵さんは少し恥ずかしそうに頬を赤らめた。
「ん? そのつもりだったよ。でも、修哉君が来てくれて助かった。やっぱり、一人よりは心強いよね」
そんなことを言われたら、僕の方が恥ずかしくなってしまう。
「なに? 本気にした?」
頬を真っ赤染めているのであろう僕の顔を見ながらくすくすと葵さんは笑う。ひどい! と僕が非難するとごめんごめんと頭をなでられた。
「でも、心強いなって思ったのはほんとだよ?」
それだけ言って、葵さんは背を向けてしまった。
大きなつばの麦わら帽子がその顔をかくしてしまうので、彼女の心中を窺い知ることはできなかった。
うまいことかわされているような気がする……。
その時、突然彼女の足が止まった。
「……葵さん?」
「…………」
「どうかした?」
僕の問いに答えるわけでもなく、葵さんは小さく何かをつぶやいた。
「さいごに見た風景だ……」と言ったような気がしたけれど、その真意は分からなかった。というよりも、考えるより先に葵さんが声を弾ませて僕の手を掴んできたからだ。
「着いたね! それじゃあ、入ろっか!」
「え? 入るってどうやって!」
今日は、午前授業だったこともあり、校舎に人の気配は無かった。
「どうやって……って、門越えるとか?」
「えぇ!?」
お茶目に言う葵さんだったが、さすがに門を超えるのは無理があると思う。
それに彼女はワンピースだ。
いくら僕が小学生だと言っても、目の前で門を飛び越えようとしたら、止めるだろう。
「というのは冗談で。開いてるよ?」
葵さんが門に手をかけると、ギィ……と錆びついた校門が音を立てた。予想外の出来事にぽかんと口を開けていると「おーい」と葵さんが僕を呼ぶ。
「早く入らないとしまっちゃうよ。ほら、早く」
「あ……ッ。ちょっと待ってよ……」
さっさと行ってしまおうとする葵さんの後を追う。
「ねぇ、葵さんおかしくない?」
「ん? 何が?」
「何って……、何で門開いてるわけ? 普通、校門って校内に誰もいなくなったら鍵締められるはずなんだけど」
確か、校長先生だかがそんなことを言っていたのを思いだす。だから、夜遅くに学校に忘れ物したからと言って学校に来ても入れないので気を付けるようにと。
「んー。先生たちにもミスがあるってことじゃないかな。それにしても、誰もいない学校って、なんだかワクワクしちゃうね?」
口元に人差し指を持ってきてこぼすのは小さな笑み。
これからいたずらでもしようかと企むような、それでいて可愛らしい笑み。
葵さんは今にも鼻歌を歌いだしそうだった。
「葵さん、子供っぽいって言われない?」
「え? ああ……。よく言われる」
また、笑顔。今度は照れ笑い。
彼女は、笑顔を絶やさない。その笑顔はとても無邪気で、僕なんかより子供っぽい。
見とれてしまうほどに。
「ねえ、修哉君。まだ第一の不思議まで時間があるから、私、ちょっと学校の中、見てきてもいい? なんだか懐かしくて」
「……うん、いっておいで」
「ありがとう。私が戻ってくるまで、修哉君どこにいる?」
どこにいると聞かれても、ぱっと思い浮かばず、目の前にある光景を指さす。二つの校舎間に挟まれたそこは、僕らが中庭と呼ぶところだった。鉄棒や平均台、花壇や鶏小屋がある、一般的に校庭と呼ばれる運動場とは違う、もう一つの校庭みたいなものだ。
「僕、そこにいるよ」
「わかった。できるだけ、早く戻ってくるね」
彼女は、麦わら帽子を僕に預けると、校舎の中へと姿を消した。
…………。
ヒューと冷たい風が吹く。空は、まだ明るかったが、ひどく気温が下がっているような気がして仕方なかった。僕の気のせいだとは思う。あちらこちらで、カラカラと不気味な音が聞こえるのも、この震えるような涼しさもきっと気のせい。
校舎の高いところに設置されている大きな時計は、四時一五分を指していた。七不思議の始まりまで、三十分はあったから、僕は、平均台にそっと足を乗せた――――。
『ふふふっ。久しぶりのお客さんだよ。とっても、久しぶり。このかわいい男の子は、私を見てどう思うのかしら……』
「――!」
不気味な声ではっと目を開けた。
どうやら、平均台の上で座ったまま眠ってしまったらしかった。日は西に傾き始めている。
「さっきの夢?」
嫌に鮮明な不気味な声。聞いたことが無いはずなのにどこか知っているような声。
あれは夢だったんだろうか。
耳元で囁かれたような感覚が耳に残っている気がして、身震いした。
ぞっとする。
もしかしてと思い、振り返るもそこには当たり前のように誰もいない。
七不思議のことばかり考えているせいだ……。神経質になっているから、あんな夢見たんだと僕はかぶりを振った。
そもそも、怪奇現象なんて……と僕は自分に言い聞かせる。
そうして、校舎の壁の時計を見上げれば、時刻は四時四十分を過ぎようとしていた。
――もうすぐ時間だ。
もう少しだというのに、葵さんの姿は見えない。
さっきの夢といい、なんだか不安になってきた。葵さんは無事だろうか……。
ちょっとだけ探しに行こうと、中庭を通り過ぎ、給食コンテナ室のわきを通った時、何かが視界の端をよぎった気がした。
赤い何かが。
「――っ?」
まさかと思い、振り返るがそこにはやはり誰もいない。
ほっと胸を撫で下ろして、コンテナ室の窓ガラスに目をやった。
「――――――!」
声にならない絶叫が響く。
窓ガラスには、
不気味な笑みを浮かべた赤いワンピースの少女が立っていた。
あまりの突然のことに窓ガラスから目を逸らす。けれど、振り返る気にもなれなくて、もう一度、窓ガラスに恐る恐る目を向けるとやはり不気味な笑みがそこに映っていた。ぶわっと全身の毛が逆立つ気がした。恐ろしさに僕の体は硬直する。窓に映るその少女から目を逸らしたいと思いながらも、そうすることは叶わなかった。
『かーごめかごめ かーごのなかのとーりは』
……!
聞き覚えのある歌詞が聞こえてくる。変に澄んだ不気味な歌声。
それは、少し昔まで遊ばれていた子供遊び。
今ではあまり聞かなくなった遊び唄。
『いついつでーやる。よあけの晩にー。つーるとかーめがすぅべったー。うしろの正面だぁれ?』
まるで、後ろを向けとでも言われているような気がした。
だけど、振り返る気にはなれなかった。
振り返ったらどうなる? 考えただけでも恐ろしかった。
窓越しの少女の顔はよくわからない。喜んでいるようにも見える。恐怖で体が震えあがった。
葵さん……。
ふと、ひまわり畑のあの黄色い背中を思い出す。
震えと恐怖に耐えきれなくなり、目を瞑ろうとしたその瞬間、後ろから自分を呼ぶ声がした。
「修哉君?」
たった数十分間離れてだけだというのに、その声の懐かしさに僕は泣き出したくなった。
再び目をよく開いて窓ガラスを見ると、心配そうにこちらを見つめる葵さんがいた。
葵さんの姿にほっとし、勢いよく振り返って、僕は本日二度目の声にならない絶叫をあげた。
僕の視界に映ったのは、優しい笑顔を浮かべた葵さんと……
その肩をがっしりとつかむ赤いワンピースの少女だった。
「うわぁあああああああ!!」
僕は仰天して腰を抜かす。震えていたばかりの足は簡単に折れ、情けなくその場にしゃがみこんだ。
「あ、……あおいさん」
声が震える。目の前の事態が現実であると認識できなかった。いや、認識したくなかった。こんなことがあっていいのか? と僕はありえないと首を振る。
「ん? どうしたの? 修哉君。そんなに驚いて」
僕の様子を不思議そうに葵さんは見る。おそらく、葵さんは気づいていないのだろう。うしろにはあの赤いワンピースの子がいる。極力そちらを見ないように僕は先を続けた。
「葵さんの肩に……」
声が震えてうまく話せない。僕は、葵さんの肩を指さす。その指も震えていた。
葵さんの肩をがっしりつかんで、彼女の陰に隠れ見えなくなった赤いワンピースの少女の様子はよくわからない。ただ、今にもぎちぎちと音がなりそうほど強く葵さんの肩をつかむ細い指だけが見える。
それにもかかわらず、葵さんは何とも思ってないのか僕を安心させようとして微笑んでいた。しかし、僕の指摘の真意に気付いたのか、葵さんが自分の肩へと視線を移した。葵さんが無表情になる。
「あら。肩が重いと思ったら」
なんて、すぐに元の笑顔に戻り、にこやかに葵さんは言う。
意味が分からなかった。
「ちょっ! 葵さん! この子! この子……!」
僕は、一生懸命赤いワンピースの少女について説明しようとする。やっと震えから解放された僕の口は、伝えたい言葉をうまく吐き出してくれない。
「ん? あ、言わなかったっけ? 七不思議の一番最初。四時四十四分四十四秒に現れる、非常階段の赤い少女」
「は?」
間抜けな声が僕の口から洩れる。七不思議の一番最初と言わなかったか? 要するに……
「その子、お化けええええ!」
また、絶叫を上げる。
「そうよ。なに驚いてるのよ? 七不思議を確かめに来たんなら、これくらい覚悟の上でしょ?」
「覚悟の上って……。いやいや、僕に霊感なんてないし、そもそも、何でホントのお化けが出てくるわけ!?」
「七不思議なんだから、お化けの一人や二人いるんじゃない?」
「え……。でも、お化け……」
まさか、お化けなんて非現実的なものが本当にいるなんて……。
「修哉君はお化けなんていないとでも思ってたのかしら。まぁ、分からなくもないけど……。でも、残念ね。この子が存在しているのが何よりの証拠よ……。大丈夫。少なくてもこの学校には害を与えるお化けはいないわ。ね? そうでしょう?」
葵さんは、赤いワンピースの子に同意を求める。いや、幽霊に同意を求めても……と思ったが、よくよく見ると、少女はただの幼い女の子だった。僕らと何ら変わらない普通の女の子だ。体が半透明であること以外は。
怖がっていたから、恐ろしく見えたのだろう。思っていたよりも少女は怖くなかった。
少女は、小さく頷く。
「害与えないとか、その子の言うことほんとに信用していいの!? だってお化けでしょ!?」
「……修哉君、お化けお化け言いすぎよ。この子が怯えてるわ」
気が付けば、少女はもう葵さんの肩をつかんではいなかった。葵さんの陰に隠れてかすかに震えている。
「……えぇ……」
気抜けした。
なんで、僕がお化けに怯えられているんだろう。さっき、死ぬほどびっくりさせられたのはいったいどっちだったか……。
『かごめかごめやろう?』
おずおずと少女は葵さんの陰から顔を出すとわずかに聞こえるくらいの小さな声でそう言った。
真っ黒な目が僕を射抜く。
少女は、僕の目をまっすぐ見つめていた。綺麗に透き通ったその目は人間であろうとお化けであろうと変わりなかった。
その目を見て僕は安心してしまった。よく見れば、自分より幼い少女。
僕は、なぜあそこまで怖がっていたのかと自分が恥ずかしくなった。
「ねえ、名前は?」
僕の問いに彼女は目を細める。
『かごめ。立川かごめ。ずぅっとね、かごめかごめをやりたかったの。私の名前の入った遊びだからね。でも、一人じゃできなくて……。だから、やろう?』
にかっと開かれた口。初めて見た少女――かごめちゃんの笑顔に八重歯が覗く。
思うに、この子が生きていたのは、僕らよりずっと昔だ。
おかっぱ頭と少し歯並びの悪い笑顔が、歴史の教科書で見た戦時中か、戦後の女の子を思わせる。
彼女がいつからここに幽霊としているのかは正確には分からない。けれど、おそらく、それくらいからということだろう。
「葵さん。やってもいい?」
どうしてそうしたいと思ったのかは分からなかった。
ただ、かごめちゃんのお願いを聞いてあげたいと思った。このまま、やりたいことをやれないままというのは、可哀そうな気がした。長年、誰ともすることができなかったのかと思うとさらにその思いは増した。
葵さんは、僕の言葉にきょとんとしたが、すぐにあの優しい笑顔に戻る。
「じゃあ、修哉君、鬼になってくれる?」
僕が預かったまま握りしめていた帽子を僕の手から取ると、葵さんはそのまま帽子を僕の頭へと乗せた。
葵さんの帽子は少し大きくて、傾いてしまう。丁度その大きなつばで目の前が見えなくなった。
「はい。これでずるなしだからね。真ん中にしゃがんで目瞑るんだよ」
手を引かれ、しゃがむように導かれる。
かごめかごめを知らないわけじゃないんだけどなぁ……と握られた手のぬくもりを感じながら照れくさくなる。
手が離れ、僕はしゃがみこんだ。まだ目を瞑っていないので前は見えなくても、足元のコンクリートと葵さんの足だけは見えた。
「かごめちゃん、準備はいい?」
葵さんの明るい声が帽子のせいで少しだけくぐもって聞こえる。
ほんの少しの間。
おそらく、かごめちゃんと葵さんが手をつないだのだろう。
「さあ、始めるよ。かごめちゃん、修哉君」
葵さんの言葉を合図に僕は目を瞑った。
すぅ……と静かな息を吸う音がしたかと思うと、葵さんは静かに、まるで赤子をあやす母親のように優しくかごめ歌を歌い始めた。それに合わすようにかごめちゃんもまた歌い始める。
かごめかごめ 籠の中の鳥は いついつでやる
夜明けの晩に 鶴と亀が滑った うしろの正面だあれ?
真っ暗な闇の中で聞こえるのは、ざっざっとコンクリートと靴が擦れる音。どこか厳かな雰囲気の漂う二人だけの遊び唄。
懐かしい子供遊び。やる人が減ってしまったこの遊びの歌詞が身に染みる。
うしろに誰が立っているかは、すぐに予想できた。
恐る恐るその名を口にする。
「かごめちゃん……だね」
目を開けて、僕は振り返る。案の定、そこには彼女が立っていた。僕と目が合うと、うしろに立つ少女は破顔した。そして、
『ありがとう』
……その一言を最後に、かごめちゃんの姿は薄くなり、ついには見えなくなってしまった。
一瞬の出来事だった。
ひゅぅっと風が、僕の背中を虚しくなぞる。
「きっと、満足して成仏したんだね……。」
茫然としゃがんだ体勢のまま動けない僕に、葵さんは視線を合わせると悼むように目を伏せた。
少しの間
ゆっくりと目を開く。視線の先は僕。葵さんは、僕の頭から麦わら帽子をとると自分の頭に乗せ、深くかぶる。そして穏やかな口調で一言一言を慎重に選ぶかのように静かに語り始めた。
「あのね、修哉君。私が、七不思議を確かめたかったのは、七不思議の原因が本物のお化けなら成仏させてあげたいと思ったからなの。たとえ、それが七不思議をなくすことだとしてもね。だからね、初め修哉君に会ったとき七不思議がなくなっていたと聞いて、ほんとはね、ちょっと安心してた」
「お化けとか、成仏とか何それ? そんなこと考えて、葵さんはここに来たっていうの?」
僕の声は少し震えていた。恐怖ではなく、たぶん、僕は泣いている。お化けなのだとしても、さっきまでここにいた少女は紛れもなく存在していたのだと僕は感じていた。だからこそ、泣いていた。
彼女がいなくなったことが悲しくて。
「他の人が聞いたら、私のこと馬鹿だって笑うかもしれない」
麦わら帽子のつばで隠れた葵さんの表情は見えない。
「でも、修哉君はここでかごめちゃんを見た。かごめちゃんがここから消えたのも。だから、私のこと笑えないでしょう? 私はね、このために来たの。七不思議にずっと縛られた霊達を元の場所に返してあげるために。でも、これは私の願い。だから、修哉君がこれに付き合う必要はない。もし、嫌になったのなら帰ってもいいんだよ」
葵さんは諭すように言う。それでも、僕は強く首を振った。このまま帰りたくはなかった。
「……帰らないのだったら、七不思議全てを教えてあげるわ」
葵さんの言葉の何かに引っかかった。でも、それが何か僕には思い出せなかった。七不思議に関するすごく重要な何か……。それは、いったい何だったっけ……?
頭に霞がかったみたいにもやもやとしてうまく思い出すことができなかった……。
ただ、僕は首を振る。
「……帰らない」
僕の答えに、葵さんはため息をつく。
「そう。それじゃあ、ついておいで」
葵さんは笑わなかった。深くかぶった麦わら帽子の中で、葵さんは僕と同じように泣いていたように見えた……。
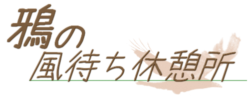


コメント