「結局、私、鷹の台に行くわ」
合格発表で私――杉田葵が掲示板の前に立ち尽くしたあの日から、早くも二十日が経とうとしていた。
受話器の先で、友人の残念そうな声が聞こえてくる。
「そっか……。高瀬高校ダメだったんだね……。」
私は、友人の言葉に頭を掻く。
「ここが東京だったら、私立でもいいんだけどさ……。こっちじゃそんなこと言えないよ。
私立は馬鹿ってレッテル貼られるんだから」
「そうかもしれないけど……」
あ……、困らせたかな? と思って、私は話題を変える。
「で、さ、彩は、合格したんだよね!!」
馬鹿みたいな空元気に見えたかもしれないけど、今の私には、そんな言葉と声しか出なかった。
「うん……。一応、第一志望に」
「そっかぁ。良かった」
見えないだろうけれど、私はこの大好きな親友に心配かけたくなくて、無邪気に笑う。
「彩が受かっててほんとうれしいよ!!」
「葵。もういいよ」
予想もしなかった返事に私は黙るしかなかった。
親友――三上彩には、私の空元気に気づいているんだ。
「本当は、悲しいんじゃないの?」
彩は、慰めるようにそう言ってくれる。
でも、違うんだ。
私がつらくて、悲しいのは、受験に落ちたことなんかじゃない。
「違うよ。彩。私、ほんとはこんな所にいたくないの。
こんなとこにいても、都会から来た私のことなんか、受け入れてくれないよ。
ただでさえ、中学校でそうだったんだ。高校に変わったからって、何かが変わるとは思えない。だから、それが悔しいんだよ」
私が、受験に落ちたあの日。
落ちたことなんか、正直どうでもよかった。
悲しいとは思わなかった。
……何より、つらかったのは、周りの田舎育ちのどうしようもない奴らの言葉。
落ちたんだって。
都会育ちのくせに。
私たちより、馬鹿だなんて。
そうささやいて、笑いあう、あいつらの姿が一番心に突き刺さった。
ただ、それだけが嫌だったんだ。
「ねえ、葵はそれでいいの?」
「え……?」
「変わろうとは思わないの?」
変わる……?
私が?
どうして?
悪いのは、皆、ここで腐ってる田舎者じゃないか。
心の中で、私自身がささやいている。
けれど、彩にそんなこと言えるはずがなかった。
「一応、努力はしてみる」
ぎこちない答えが口の中で転がる。
そんなこと、心では片っ端も思っていないのに。
「頑張れ。葵。
葵なら、鷹の台で頑張れるよ!!」
応援してくれる彩に返す言葉はなかった。
「うん。ありがとう」
受話器を静かに置くと、私はベットに倒れこむ。
目線の先には、セピア色のセーラ服にオリーブ色のスカーフがあった。
明日から始まる、しようもないド田舎の高校、私立鷹の台高校に対して、嫌気がさしながらそれを見つめた――――――
***
「田舎とは聞いてたけどねぇ……。ここまで田舎だと嫌になる」
自転車で息を切らせながら走る私は、変わらない風景に舌打ちをする。
……なんだ、これは。
それ以上の感想はもはや出てこないだろうと思った。
どこを見ても、一面茶色の風景が続いている。
あっちも、こっちもまだ土が表面に出たままの田んぼばかりだ。
それ以外、何もないこのド田舎はいったい何なんだろう。
嫌になって、上を見上げたその時、遠くから、何かを叫ぶ青年の声がした。
「ごめんっ! そこの人、ちょっとそれとってくれない?」
突然の声に、私は急ブレーキをかけ、前方を見た。
普段、遠くを見るには眼鏡が必要な私には、セピア色のブレザーが風に揺れるのがわずかながらわかる程度だった。
あの制服は、今、私が来ているセピアのセーラ服と対になるもの。
つまり、同じ高校の男子らしかった。
「そう! 君。そこのペットボトルとってよ!!」
君というのは、どうやら私らしい。
下を見ると、青年のものらしきペットボトルが落ちていた。
……どうせ、急いで走りすぎて、自転車のかごから落ちたかなんかだろう。
ため息を漏らして、それを拾うと、彼のもとまで自転車を進めた。
「はい。」
近づいて、ペットボトルを渡すと、青年はその茶色の髪を揺らしながら、ニコッと微笑んできた。
「ありがとう。……君も鷹の台? 女子セーラなの?」
「え?」
急な質問に、私は困惑する。
ただ、質問の内容的に彼は同い年だということは分かった。
「……一年?」
「うん。そうだけど。君もでしょ?」
これで、もし私が先輩だったとしたら、確実にこいつを殴り飛ばしているに違いないが、同じ一年なので、作り笑顔を浮かべながら、ペダルに足をかけた。
「そうよ。」
端的にそれだけを返すと、彼に背を向け走り出した。
……こんなことしている場合ではないのだから。時計を見ると、すでに、登校時間5分前を切っていた。
「さっきの奴、間に合うのかな?」
ふと、気になって後ろを向いたときには、あの茶髪は見えなくなっていた――――。
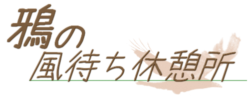

コメント