校舎を歩きながら、葵さんはこの学校の七不思議ができた経緯を教えてくれた。
「ねぇ、修哉君。この学校の七不思議、どうしてできたと思う?」
「それは……普通に考えたら、不思議なことがあったから、自然と広まって七不思議なんて呼ばれるようになったんじゃなくて?」
葵さんはそうだよねとでも言いたいようにくすくす笑う。その表情を見るに僕の答えは違うということなんだろう。
「違うの?」
「どうだろうね?」
面白がっているんだろう。そういう笑みだ。
中庭から第二校舎に入ってすぐの階段を上って、中庭を挟む二つの校舎――第一校舎と第二校舎をつなぐ渡り廊下を歩く。渡った先は第一校舎だ。職員室や音楽室、図書室など特別教室が集中しているのがこの校舎だ。
こつこつと誰もいない校舎に二人の足音だけが響く。反響して誰かがついてきているような錯覚をするけれど、そんなことはない。振り返ってもきっと誰もいないだろう。
第一校舎に渡りきって、廊下を歩き、職員室脇を通る階段へと向かう。
「さて。こっから、ちょっと遠回りだけど、第二の七不思議の場所に行こうか。職員室前だから、この下だね」
「なんでわざわざ二階から遠回りして一階に?」
第二校舎から入らず、第一校舎から入ればよかったのでは? と疑問を口にすると葵さんは曖昧に微笑む。
「第一校舎の入り口に鍵かかってたのよ。こういうとこはちゃんとしてるくせに校門を開けっぱなしにしてくなんて、ほんと先生たち抜けてるよね」
あははと笑いながら、葵さんの目は笑っていなかった。なぜだろうと考える暇もなく話題が変わってしまう。なんだか、はぐらかされたような気がした。
前にもこんなことがあった気がしたけど気のせいだろうか?
「そういえば、七不思議がどうしてできたかって話だったよね」
「え!? あ、うん……」
ついさっき流されたばかりの話題に急に戻る。確かに、こちらの方が本題だった。
「もともとね、この学校に七不思議なんてなかったんだ」
んーと葵さんは伸びをする。
「なかった?」
「そう。私の知る限りはね」
一階へと向かう階段を下りはじめたころには空はオレンジ色になっていた。窓から夕日が差し込んでくるのを、僕は眩しくて目を細めた。
葵さんは一呼吸置くと話を続ける。思い出しながらゆっくりと。
「ここの学校に七不思議ができたのは私が小学六年、丁度、修哉君と同じくらいの時ね。その時にできたの」
階段が終わりに差し掛かった時、葵さんは一瞬、僕を振り返ると、ニヤッと笑みを漏らしてそのまま駆け出した。まるで、追いかけておいでと言ってるみたいに。
慌てて後を追うと廊下に設置されている消火栓の前で彼女は足を止めた。
「ほら。あった」
弾むような声を追うと、葵さんは喜ぶように消火栓を指さしていた。
真っ白な消火栓。
そして、対比的な赤。
そこには真っ赤な手形がべったりとついていた。
「これが、二つ目。設置消化栓の落ちない血の手形」
葵さんはどう? というようにこちらを見る。どうといわれても正直困った。
「これが二つ目? なんか、イマイチだね……」
あまり、面白くはなかった。
というのも、その血の手形というのがどっからどう見ても絵の具でつけただろうというくらい真っ赤だったし、手の大きさがいかにも小学生だったからだ。少なくても、血ではないというのはすぐわかった。
落ちないのはおそらく水性の絵の具じゃないからだろう。
「ね。イマイチでしょ? こういうことよ」
葵さんは独りでに納得する。僕にはよくわからない。首をかしげると葵さんはふふっと笑みを漏らす。
その笑みに僕は問う。
「え? どういうこと?」
「この七不思議、誰かが作った七不思議なのよ」
葵さんが赤い手形にそっと触れる。案の定、手形は完全に固まっていた。
「確かにかごめちゃんのように本物の幽霊もいた。けど、全部じゃない。数が足りなかったのかな。この七不思議、あからさまにでたらめなのがいくつか存在してるの。これはそのうちの一つ」
葵さんはしゃがみこむと懐かしんでいるのか、赤い手形と自分の手を合わせてみたりしている。
「ちょっと待って。要するに、この学校の誰かが七不思議を作ったってこと?」
「そうよ。どうして作ったのかは分からないけれど、気まぐれかなんかだったんじゃないかな……」
そういった声音はなぜか少し悲しそうだった。
「七不思議が広まった当時、確かめようとした子が何人かいたの。当たり前よね。聞いたら確かめたくなるのは。修哉君もその一人のようだし?」
「う……」
心中を言い当てられ、返す言葉もなかった。
けどねと葵さんは続ける。
「そんなことをいう私もそのうちの一人かな。七不思議なんて、ちょっと面白そうじゃない? だから、確かめたくなるよね。それで、確かめに行った人たちは決まってこう言うの。七不思議を管理する女の子が出るって」
くすっと不気味な笑みを漏らす葵さん。
再び、僕は首をかしげる。
「その女の子って幽霊?」
「さぁ、どうだろう? でも、その少女が作ったって言われるのが通説だね。その子、七不思議を確かめにくる人たちにいたずらしていたから」
「葵さん、その子に会ったことあるの?」
思い出し笑いをし始めた葵さんはツボにはまってしまったらしく、しばらく笑い続けていたけれど、僕のその問いかけにピタっと笑うのをやめた。
「ううん。私はないよ。でも、知ってはいるかな」
葵さんは立ち上がった。スカートをパタパタと払う。ゴミはついてないはずなのに。
「知ってるの!?」
僕が声をあげると葵さんは驚いたのか、一瞬びくっと肩を上げると、
「それはだって……」
と恥ずかしそうに頬を掻いた。
「七不思議を確かめに私自身も行ったし、他の子が脅かされて酷い顔で逃げていくのも見たことあるしね」
つまらない答えに、なんだ……と僕はガッカリする。
「知ってるって、ほんとに知ってるだけなんだ……。てっきり、知り合いか何かかと思ったのに……」
ぶーぶーと抗議の意を示すとごめんごめんと頭をなでられる。そういえば、こうやってなでられるのは二回目だ。まるで、怒らないでと言われているようだった。
「ごめんね。あんまり、有力なこと言えなくって」
「い、いいけど……」
僕はそっぽを向く。そんな悲しそうな手つきでなでられたら、これ以上言える言葉はなかった。
「それじゃあ、気を取り直して次いこっか」
そっぽを向いた僕の手を取ると葵さんはほんの少し強めにぎゅっと握った。
「葵さん?」
その力の込め方がなんとなく気になって振り返ってみると、葵さんの不安そうな顔があった。青白いようにも見える。
よくよく見れば、握られた手もほんの少し震えている。
もしかして、具合が良くないのだろうかと心配になってしまいそうな様子だった。
「……大丈夫?」
「何が?」
葵さんは笑って言うのだけど、大丈夫そうには見えなかった
「葵さん具合悪い?」
「そんなことないけど……どうかした?」
逆に僕が心配されてしまう。いや、違う。やっぱり、葵さんはあんまり具合が良いようには見えない。
「だって、震えてるから……」
事実を言う。葵さんの手はこうして話している間も震えていた。
僕の指摘に葵さんは慌てて、僕の手を放すと自分の背に手を隠してしまった。そして、ぶんぶんと首を振る。
「あ! ち、違うの!! ご、ごめんね。次の七不思議、実は苦手で……」
「え?」
思いもよらない答えに僕は苦笑いするしかなかった。
苦手で震えるようなものがあるのに、この人は、僕が一緒に行くって言わなかったら、一人でこの学校に来るつもりだったのだろうか……。
なんだか、情けなくなって僕は笑いをこぼす。
こんなところが葵さんらしいと思ってしまった。
たぶん、笑顔で明るい葵さんのことだから、何にも考えてなかったんだろうなと妙に納得してしまったのだった。
「葵さんでも、苦手だったり震えたりするんだ」
おかしいと僕が笑うと、葵さんもつられて笑ってくれる。
「ごめんね。驚かせちゃって。女の子だからね、苦手なものも怖いものもあるよ」
改めて、葵さんは僕に手を差し出す。
その手は震えていなかった。
笑いあったからだろうか。少しは不安が和らいでくれたならよかったと思う。
僕はその手をぎゅっと握る。いざ、意識して握ると葵さんの手は僕より大きいけど、細くて白くて今にも壊れてしまいそう手だった。
なんて思っていると、ふふっと葵さんが笑い出す。
「どうしたの?」
「ん? なんだか、嬉しくって。やっぱり、修哉君いてくれてよかった。王子様みたいで心強い」
ドキッと心臓が鳴る。王子様って……。
「いや、あのさ、葵さん、さっきかごめちゃんのとこでも見て分かってると思うけどさ、僕も相当怖がりだからね……。葵さんみたいに強くないからね」
悲しいことに、僕は相当怖がりだし、葵さんが苦手というものを怖がらずに済む自信なんてなかった。
王子様だなんて、そんなことこれっぽっちもない情けない男なんですと心の中で続ける。
ただでさえ、いつも女男なんてからかわれている僕だから。
「それでも、本当に心強いんだよ」
満面の笑みで葵さんは言った。見とれてしまう笑み。
「それじゃ、次行こう!」
また、いつものように元気そうに葵さんは僕を引っ張っていく。
「葵さん、次はどんな七不思議なの?」
苦手というのだから、どんな怖い七不思議なのだろうと疑問に思った故の問い。
葵さんは低い声音で、こう言った。
「第三の七不思議、第一校舎の中央階段踊り場の笑う鏡」
なぜだろう。
その一言にぶわっと嫌な汗が流れ出てくるのを感じた――。
七不思議の少女 <第二の七不思議 設置消化栓の落ちない血の手形>
 七不思議の少女
七不思議の少女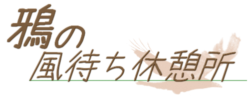
コメント