「『桜の樹の下には屍体が埋まっている』、なんていうけれどね」
なんて、声に出してみる。
独り言?
いいや、違う。
僕が何かを呟けば、聞いてくれる人物がいることを僕は知っている。それを信じて疑っていない。
だから、今日もきっと彼が聞いててくれるだろうと思って、僕はそのまま続ける。彼の姿を確認するわけでもなく。
「あれはね、世にある神秘を不安がった人間が神秘の理由を理解した結果の言葉で、そういう物語の一節だったような気がするけれど」
桜の花びらがちろちろ落ちてくる。
思わずそれに手を伸ばす。
重力とは勝手なものだ。
僕に降ってきてるわけでもないけれど、どうあっても、重力のせいで僕ら地に足を着けてる人間の元に降ってきてるように錯覚させてくる。
僕の元に降ってきたのかななんて、勝手な解釈をしてみてるわけで。
解釈とは、自分勝手で自由なものだ。
彼が僕のこんな独り言を真面目に聞いてくれてるだろうと思うのもきっと勝手な解釈なんだろう。
「神秘って理由がはっきりしないだろ? それって気持ち悪いじゃないか。だから、その男はこう解釈したわけだ。そういう現象の裏にはきっと臭くて残酷ではしたない真実があって然るべきだ、ってね。そう解釈することで、きっと彼は安寧を得たんだろうね。なんて、これも僕の勝手な解釈だよ」
言葉にできないほど美しものにはそれ相応の理由があってほしい。
生き生きしたものの裏にはきっと冷たい死がある。
説明のできないものは異様で、恐ろしく、不安に思う。
美しいものに醜さの欠片もないなんて許せない。
だから、説明をつけたいのが人間ってものだ。
と、僕は思う。
そして、僕もまた、そういう人間なんだ。
「まぁ、だから、なんだという話なんだけどね。僕はね、きっとこの美しい桜の木の下には死体が埋まってると思うんだ。この場合、僕が説明をつけたいのは、美しい桜というものでもなく、神秘でもないけれど」
桜の花びらを拾って、その花の根が沈む土を見る。
我が家にある桜の木はこの近辺ではひと際綺麗と噂されている。
とはいえ、誰も我が家に近づく気なんてないから、この桜の木は実質我が家が独占したようなものだ。
実際、我が家の敷地内にあるので、我が家のモノではあるけれど。
僕は思う。
この桜の木の下にはきっときっと死体が埋まっている。
「何が言いたい?」
ここまで話して、初めて後ろから声が返ってきた。
彼は僕が悲観的なことを言おうとしている時に限って口を挟むのが好きらしい。
必ず、僕がそういうことを口にする前に口を挟まずにいられないのが、この静かな隣人だ。
気配も全くしないくせに、こういう時、決まって彼は僕の振り返ればすぐに見える範囲にいる。
さっきまで誰もいやしなかったにも拘らず。
でも、振り返らない。
振り返らなくても、彼がそこにいるのは分かるし、第一、振り返ると彼がきっと悲しそうな顔をしているに決まっているからだ。
感情なんてないと口にする彼だけど、僕がこういう話をすると、悲しそうな顔をする。
どっちかと言えば、そんなことを言うなと止めたい顔をしている。
だから、見ると止められそうだし、見ない。
見たところで、やめろなんて口にして来ないけれど。
愚痴くらい溢させてよ。
そんなことくらいしかできやしないのだから。
「ハリス」
彼が僕の名前を呼ぶ。
顔なんて見なくても分かった。
それ以上言うなって言外に言ってる。
でもね、言わせてほしい。
「僕は思うんだよ。この桜の木には死体が埋まっていて、だから、アーカンウェウェ家はきっと呪われてるだ。そうでも言わないと納得できないじゃないか」
そこまで言い切って、僕は振り返る。
物静かな隣人は、やっぱり、そんなことを言うなと言う顔をしていたけれど、僕の顔を見たからか、それ以上のことは口にはしなかった。
「アーカンウェウェには男は生まれない。僕はこの家の唯一の“嫡男”だけど、結局この家の呪いは解けちゃいない。解けっこない。それは、きっと、このやけに美しい我が家の桜の木の下に、僕らアーカンウェウェを許さない誰かが埋まってて、一生呪ってるからなんだ。その代わりに美しい桜が咲くんだよ。きっとね」
ほんと、馬鹿げた解釈だと自分でも思う。
けれど、そうとでも理由をつけていたかった。
そうじゃないと、“僕”がこんな目にあわなきゃいけないことを納得できない。呑み込めない。
「泣くな」
隣人が言う。
泣いてなんか……と言いかけて、やめた。
あれ……おかしいな。
泣くつもりなんてなかったのに。
それに、ものすごく身体が痛い。
「うぅ……。うぅう……」
ズキンと痛む身体を抱きかかえる。
立ってるのも辛くて、地面に膝をついた。
隣人が駆け寄ってくる。
君さぁ、感情なんてないとか言いながら、今、僕の心配して凄い顔してるんだけど、気付いてる?
「馬鹿……。そんな身体で出歩くな」
彼に……、フィーンドにそう言われて、自分でも自分の愚かさに笑いたくなった。
ボロボロ涙が落ちてくるほど身体が痛かった。
「あ、は、は……。でも、部屋にいれなくて。だったら、この桜でも見て気を紛らわせようかな……、って思って」
痛い。
フィーンドが身体を支えてくれてるので、幾分かマシになったけど、それでも身体が痛くて痛くてたまらなかった。
文字通りぼこぼこにされた。
顔だけは無事だけど、服で隠れるあらゆるところが傷だらけで痛い。
日課みたいなもので、痛くなくなってもいいのにな……。
何で痛みって、どんなに慣れたつもりでも痛いんだろう。それと、どうして怖さっていうのも慣れないんだろう。
人間の体って不便だ。
嫌だな。
笑ってたいのにな。
「ご、めんね。そろそろ慣れたいな……。僕が悪いのに。僕が嫡男だから悪いんだ。母さんも父さんも姉さんたちも誰も僕を嫡男なんて認める気がないんだ。でも、僕は……“嫡男”だから。嫡男だから、耐えなきゃいけないんだ」
毎日、毎日、家族の誰からか暴力を振るわれる。
僕が“嫡男”であることに納得がいかないから。
僕が“嫡男”足りえていないから。
僕を“嫡男”とも思ってないから。
いろんな理由でいろんな暴力を振るわれる。
とても口になんてできないけれど。
ほんと、気持ち悪い。
先程まであったことを思い出すだけで吐き気がこみ上げてくる。
それを忘れたくてこの桜の木に足を向けたのに。
傷が、疵が痛くて痛くてたまらない。
でも、弱音は吐かない。吐いてはいけないと言われてきたから。それは“嫡男”のやることではないから。女々しいなんて言われてはいけないんだ。少なくても、“僕”は。
そうでなくてはならない。
だから、痛みと涙を堪えなくては。
「フィーンド。もう、いい」
彼の手を振り払う。
もう支えなくていい。自分の身体くらい、自分で支える。
痛くない。痛くなかったはずだ。
そう、自分に言い聞かせる。
フィーンドの身体から離れて、立ち上がる。
息が荒れそうなくらいきっと痛い。
でも、そう言ってたら生きていけない。ハリス・アーカンウェウェは。
目の前が眩む。
なのに、地面に落ちる桜の花びらがやけに美しくて、それだけが心を癒してくれる。
古い作家が、この木が美しいのは桜の木の下に死体がいるからだと言ったけど、それが今はよく分かる気がした。
こんな美しいものの下にはきっと凄惨なものがあって然るべきだ。
だったら、醜い僕も美しく見えたらいいのにと思うのは、間違いなく傲慢だね。きっと、醜い僕を踏み台に、アーカンウェウェ家は美しい女の園であれるんだろう。それなら本望なのかもしれない。
“僕”がいるから、この家は美しくあれる。
多少、不気味であれど、この家の女が美しいのは事実だ。
“僕”は日頃投与される薬のせいか美しくないけど。
あぁ、ほんと。ムカつくくらい綺麗だよ。この桜は。
癒されたのに、また嫌な気持ちになってきた。
ぐるぐる良くない思考が頭を回している。薬のせい? それとも痛みのせい? さっきの父親の気持ち悪い行為のせい? よく分かんなくなってきた。
「ハリス」
まーた、彼が僕の名前を呼ぶ。
まだ何も言ってないだろ。
だから、そんな捨てられた子犬みたいな声を出さないでよ。
違う。
だめだ。良くない方向に思考がいってる。
だから、彼は僕の名前を呼ぶんだ。
戻ってこいって。
僕は……、僕が一番、“僕”が分からないよ……。
僕が……、僕が、分かる、ことは……。
「桜の……木の下」
そこまで呟く。
低下してる思考を何とか戻そうと、頭を違う方向へと向かわせる。
そう。桜の話。
桜の話ならまだ出せる。
彼は、何も言わず、続きを待ってくれていた。
頭がぐちゃぐちゃになってる僕の話なんて、聞いても意味がないのに、彼はいつだって聞いてくれる。何も言わずに。
彼のそういうところには救われる。
……アジェンが、僕を気にかけなくなってからは、彼が唯一の僕の話し相手だ。
「桜の木の下に……、死体が埋まってるって言われれるようになったのは、桜の花と茎の色のせいだ……っていう話もあってね」
ズキンズキンと頭が痛む。
無理に思考を別な方に持っていこうとしてるせいだろうか。
それでも、“僕”……は、僕で……いや、“私”でいたい。
だから、回らない思考を必死に回す。
それをやめてしまったら、きっと、僕は“自分”を保てない。
思考を回して、回して。
桜の話を絞り出す。
「桜染めって知ってる? というか、今、僕が持ってるこれがそれなんだけどね」
と僕は自分の肩に掛けていたストールを指し示す。
少しずつ、荒れた息と思考が戻ってきている気がした。
あぁ。思えば、このストールはアジェンがくれたものだった。
最近、彼とは碌に会話をしていない気がする。
昔は、この木のそばにある塀に空いた穴からよく彼が僕を呼んでいた。
僕が暴力を振るわれるたびに、元気づけてくれていたのは彼だった。
彼が来なくなってから、彼がいてくれる時間だけは痛みも辛さも忘れられたんだと今更になって気付く。
『桜の咲く季節に生まれたハリスは、桜が似合うよ』
そう言って、彼がくれたのがこの桜染めのストールだった。
まだ肌寒さが残るから、身体を冷やさないようにと。
だからだろうか。このストールはほのかに温かい気がした。
「ハリス」
またフィーンドが僕を呼ぶ。
話の先を催促しているのか、それとも、僕の思考がまた暗い方にいってると言っているのか。
真意は分からない。
でも、思考は暗くはなかった。
むしろ、あの日々が懐かしくて、少しだけ元気が出たんだよ。
もちろん、少しくらいは落ち込んでいるけど。
もし、まだアジェンがここに来てくれていたら、僕はまだ笑っていられるのかもしれないとは思うから。
でも、その時の思い出があるだけで、僕は満足しようと思う。
あの日々が少しだけでもあった。全くなかったわけじゃなかった。
あの日々がなければきっと僕はここまで生きていなかった。
だから、それだけでいいと思えば、切なさは幾分かマシになると思うんだ。
「ごめん。ちょっといろいろ思い出しちゃって。それで……、この桜染めの話だったね」
僕は足元に落ちている折れた桜の枝を拾う。
「桜染めは桜の花じゃなくて、枝でするんだ。枝を水に浸して、煮詰めてできる染液が見事なまでに赤褐色なんだよ。まさに血の色みたいね」
自分がつまみ上げている木の枝を見つめる。
この枝の中には鮮血が詰まっていて、今にも滴ってくるんじゃないかと思えてくる。
「だから、桜の木は土の下に埋まった死体から血を吸いつくして、その根に幹に枝に花にその血を通わせてるんじゃないかって言われてるんだよ」
桜が脈打つことはないと思いながらも、もし、その血を通わせているのなら、脈を打つ音が聞こえるんじゃないかと、僕は桜の木に耳を当てる。
とくとくと耳元で聞こえる。
はっ!? と勢いよく桜から耳を離した僕をフィーンドが不思議そうに見ている。
「桜に血が通ってるんじゃないかって、耳を当てたら脈打つ音が聞こえた気がしたんだけど、そんなわけないよね」
と僕は笑ってみたけど、確かに聞こえた気がした。
そんなわけ……、ない、よね……?
どくどくと僕の心臓が鳴る。
ちょっとだけ、桜の木が怖くなって後ずさる。
僕が怖がってるのが分かったのかフィーンドが僕と桜の木の間に割り込んでくる。
「フィーンド……?」
フィーンドは何も言わない。
僕を桜の木から庇うように立っているその背中しか見えないので、彼が何を思っているのか分からない。
「……」
フィーンドがそっと桜の木に耳を当てる。
彼は顔色も身動きも何一つ変えなかったから、脈打つ音が聞こえたか否かは分からなかった。
けれど、フィーンドは振り返ると僕の頭を軽く掴んできた。
「……? 何?」
鷲掴みされてるけど、別段痛くはない。
?
何がしたいのかよく分からない。
こういう時、彼が物静かなのは困る。
ちょいちょいと鷲掴まれた頭を下に傾かせられる。
ん? 屈めってこと?
よく分からないまま、僕は屈む。
そしたら軽く頭を引っ張られて身体が傾いた。
「ねぇ、ちょっと!」
痛いんだけど!? いや、思ったより痛くないけど、ただでさえ身体が痛いんだから、勢いよく動かさないでよと抗議の声を上げる。
でも、フィーンドは何も言わない。
どくっと何かが脈打つ音が聞こえた。
!?
僕が状況を把握しようと顔を上げると、フィーンドの顔が真上にあった。
とくとくと脈打つ音が耳元を撫でていく。
僕の耳元で脈を打っていたのはフィーンドの心臓だった。
どうやら、僕はフィーンドの胸に耳を押し当てられる態勢になっていたようだった。
「何?」
よく分からないんだけど。と、僕は間近のフィーンドの目に訴えかける。
「木から脈打つ音がするわけないだろ」
珍しく彼が発した言葉は彼の胸から僕の耳を通して響いてくる。
君ってそんな声してたっけ?
彼の穏やかな心音のせいか、いつもより彼の声が穏やかな気がした。
「フィーンドには聞こえなかったの?」
僕の問いに彼は頷くわけでも首を振るわけでもない。
「大体、脈打つ音がどんな音かも分からない癖によく言う」
と彼は言う。
意味が分からないと僕が言おうとしたところで、彼の心臓の音がやけに耳についた。
とくんとくんと心臓が跳ねている。
あれ……?
先程聞いた桜の脈打つ音がすぅっと頭から描き消えていく。
本物の心音とは似ても似つかない。
あれは、僕が勝手に聞こえた気になっただけの音だったような気がするほど、本物の心音は暖かくて、優しい音をしていた。
その音が心地よくて、僕はつい長い時間その音を聞いていた。それでも、彼は一つも文句を言わなかった。
「ハリス」
僕の名前を呼ぶ振動まで伝わってくる。
「そんな妄執にとらわれるな。桜が綺麗なのは、死体が埋まってるからでも、その血を吸いつくしてるからでもない」
珍しく彼が饒舌だった。
彼は僕に胸を貸したまま、僕を支えたまま、桜の木に手を伸ばす。
その手の行く末を僕も目で追いかける。
桜の木はちらちらとその花を散らせていた。
やっぱりその花は綺麗で。
まるでこの世のものとは思えない。
けれど、この桜はちゃんとここに、この世に、存在している。
「お前の誕生を祝うために綺麗なんだよ」
あまりに彼の言葉が彼に似合わなかったから、僕は耳を疑う。
「今なんて……?」
僕が再度言って欲しいと促すと彼は嫌だと言うようにそっぽを向いた。
可笑しい。
君、そういうこと言わないでしょ。何言ってんの。と、つい笑みがこぼれる。
そしたら、軽く頭を小突かれた。
僕が彼を見上げると、ちょっとむくれていて、それがまた可笑しくて、僕はたまらず吹き出す。
「お前……」
「だって、君が可笑しいこと言うからでしょ」
ロマンティックすぎる。本当に似合わない。
でも、それでこぼれた笑みは心地よかった。さっきまでごちゃごちゃになっていた思考も、身体の痛みもすべて忘れさせてくれる気がした。
「この花が、僕の誕生を祝ってる、ね」
さっき脈打って聞こえたのが幻聴だったとして、それを納得できるかと言われると難しい。
そんな、僕の都合で花が咲いてくれたら、どれだけ神様からの祝福を受けているって言うんだ。いや、この世界において、神は“神族”が唯一の神で。この神様たちはこの世界を壊そうと思っているという。
そんな神様が僕の誕生を祝福してるだなんて、励ますにしてももっとマシな嘘があるでしょ。
「励まし方へたくそでしょ、君」
「そんなことはない」
相変わらず今日の彼は饒舌で、僕の言葉を即座に否定するもんだから、面食らう。
「どうしたの、君らしくないけど」
僕が彼に問うと、彼は静かに目を閉じた。
「?」
「お前が、たとえ、自分が神から見放されてると思っていても、“神様”はちゃんとお前を祝福してる。だから、そんなに悲しいことばかり言うな」
優しく頭を撫でられる。
何度も何度も。
まるでお母さんが子供をあやすかのように。
本当の母さんにそんな風にされた記憶はないけど、きっと普通の子供だったら、こんな風に優しく撫でてもらうこともあったのかもしれないと、その手を受け入れて、されるがままにしておく。
目を閉じ、優しく頭を撫でる彼は、どこかの本で見た神様にそっくりな気がした。
そういえば、彼は、正真正銘の“神様”だ。
彼は、『自分は神族の成り損ないだ』と言っていたけれど、彼もまた“神族”だった。
彼には僕がアーカンウェウェ家の嫡男としての役割を果たせるかどうか見張るためだけに神族から派遣された見張り役という役目があって、別に僕に優しくしてくれる理由も、こんな話を真面目に聞いてくれたり、答えてくれる義理なんて全くないのだった。
それでも、こうやって会話を交わしてくれて、挙句、僕にここまでのことをしてくれる彼はいったい何だと言うのだろう。
僕の知る限り、神族は冷酷で、人の気持ちなんて微塵も考えない傲慢な神様のはずなのに。
彼はあまりに優しすぎる。
それはずっと前から知っていたけれど。
それにたくさん自分が甘えてきたことも自覚している。
それに救われてきたことも。
「“神様”が僕を祝福してるって、その“神様”ってもしかして、君?」
こういうのも甘えてるのかもしれないと思う。
冷静に考えて、神様を揶揄う人間ってかなり無礼な気がするけど、これも彼が優しいからできることだと理解している。
それに甘えているんだ、僕は。
でも、彼はちっとも怒りもしない。
彼の言葉を借りれば、感情がないからということになるのかもしれないけど、言うほど、感情なくはないんだよなぁと思う。
さっきもむくれてたし。頭小突くし。
まぁ……、人に比べ感情は顔には出ない方だと思うけど。
少なくても、僕は僕以外の前で彼の表情が変わる姿をあまり見たことがないから。
そんな彼は、静かに目を見開いて僕を見下ろしていた。
エメラルドグリーンの瞳が僕を覗く。
この世界の神様の目の色だ。
「さぁ、どうだろうな」
僕を見下ろす“神様”は優しく微笑んだ。
「誕生日、おめでとう。ハリス」
彼が呟いたその言葉は、僕の一番近くにいる優しくて不愛想な“神様”からの祝福だった。
桜の花が風に揺れ、“神様”は一層神々しく見えた。
「そっか。今日、誕生日だったね」
まもなく日付が変わる。
今日一日、誰からも祝われなかった誕生日。
僕すらも忘れていたそれを彼が思い出させてくれたのだった。
彼の後ろで月に照らされている桜が、今だけは、僕の誕生を祝福するために咲いてくれていればいい。
血生臭い事実なんてなくても、美しく綺麗なものがあってもいいのなら……。
それはきっと、僕が生きていてもいいということだと思った。
あまりに自惚れが過ぎるけど、僕の傍の“神様”がそう言ってくれたから――。
***
ハリスに心音を聞かせてやったら落ち着いたのか、『僕はもう眠るよ』と自分の部屋へと帰って行った。
『誕生日、祝ってくれてありがとう』と言っていたが、こんな日が変わる直前まで誰にも祝われなかったことが不憫でならなかった。
俺の言葉くらいでハリスが救われるとは思わない。
それでも、少しでも気休めになればいいと思った。
にしても……、日に日にハリスの体調が悪化していることが気にかかる。
気丈に振舞えないくらいには最近は体調が悪そうだ。
ハリスがいなくなった後、俺は、桜の木に触れる。
……。
ハリスには妄執にとらわれるな、などと言ったが、明らかにこの桜の木は脈打っている。
耳を当てれば、疑いようもないほど脈打つ音が聞こえる。
「これは……一体、何なんだ……?」
まさか、ハリスが言うように、死体が埋まっていて、その血を吸い尽くして生きてるとでも?
そんな馬鹿な。とは思う。
でも、これは幻覚でも幻聴でもない。
紛れもない、事実だ。
それがあまりに気味が悪い。
「“神様”、な」
ハリスにああは言ったが、それが“俺”だとは言ってない。
あの時。
ハリスが桜の木に耳を当ててのけぞった後、俺がこの桜の木に耳を当てた時に感じたモノは、優しい祝福に満ちた“何か”だった。
それが何だったのか説明を求められても、俺には説明することができない。
この世界における神である神族の、成り損ないとは言え、俺も神族であることは確かで。神族に分からない事象などあってはならない……はずだ。
とはいえ、例外もある。
この世界に神族ではない“何か”が作った四つの宝“四大宝”がそれだ。
そんなものは本来ないはず、なのだ。
少なくても父……、神族の長“レン・オルデン”が言うには。
それでも、この世界には神族が干渉できない何かがある。俺が桜の木に耳を当てて感じたモノはまぎれもなく、“それ”だった。
“それ”が何かは理解できなかったが、少なくても“それ”がハリスを傷付けるどころか祝福しているのが、何故か俺には分かった。
だから、ああ言ったんだ。
俺でも、神族でもない、けれど、きっと俺達神族が干渉できない“神様”がこの世界にはいて、それがハリスを祝っているぞ、と。
ハリスはそうは思えなかったかもしれないが、それは紛れもない事実だった。
少なくても、俺にはそう確信できる。
だから、ハリス。
どうか、誰からも、神からも見捨てられているだなんて思わないでくれ。
そう伝えたかった。
きっと、そこまでのことは伝わらなかったと思うが、少しでも伝わっていたらいいと、思った。
俺はハリスの想う“アジェン”にはなれないし、俺はあくまでも監視役でハリスを救うことも助けることもできない。
だから、もし、本当に先程感じた“何か”が“神様”であったなら。
どうか、ハリスをこれからも守ってほしい。
この桜の木がその“神様”なら、どうか、ずっと、ハリスを見守っていてくれ。
と、脈打つ桜の木に、本来であれば、神族という神様の一端である俺が、すること自体あり得ない“祈り”という行為を捧げるのだった――。
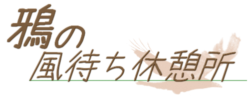


コメント