手を伸ばす先なんてどうでもよかったんだけどな。と彼は笑った。
かつての凄惨な日々をまるで忘れてしまったように清々しい笑顔だった。
「そうか……」
自分とそっくりな姿をした彼に俺から返せる言葉などなかった。
「お前にそういう顔をされると腹立つけどな」
と、彼は悪態つく。
本当に返す言葉もない。
そりゃそうだろう。
”お前”をそういう姿に変えたのは紛れもない俺だから。
憎まれこそすれ、そんな笑顔を向けられていい存在じゃないことくらい自分でもわかっている。
そして、俺には彼に同情する権利すらないだろう。
だから、そんな顔をするなと言われるのは当然だ。
ただ……、彼が手を伸ばした先が俺達でよかったのかと思わないことはない。
もし、俺達でなければ、彼は知らなくていい真実を知らないままでいれたのではないかと。
そう、思わずにはいられなかった。
「ただ……、手を伸ばす先なんてどうでもよかったと言っても、伸ばした先がお前らでよかったとは思うよ。そうでなければ、僕は今でもまだあの籠の中だろ」
彼の視線が晴天に向けられる。
籠なんて言ってるが、あそこは窓も扉もない箱だろう。
格子なんて生易しいものじゃない。鉄の壁に囲まれた箱だ。
そう思うと、きっと彼に見えているこの晴天は一層綺麗なのだろうなとその視線を追った。
あぁ、綺麗な空だ。
何もかも笑えてしまえるくらいに清々しく。
「お前らに手を伸ばすまで、僕はずっと考えてたんだ。僕に手を差し伸べてくる奴なんてどうせ碌でもないだろうと。だから、僕はこう思ってたんだ。手を伸ばす先なんてどうでもいい。手を伸ばしてきた奴らの手をへし折って、噛み千切ってやる。どうせ、僕を助ける奴なんていないってな」
だけどさ。と彼は笑う。
「さすがに、手を伸ばしてきた由紀の顔を見たら、そんな気失せたよ。分かるだろ?」
彼の言葉におおむね納得しかできない。
どちらにせよ”俺”であれば、あの顔に逆らえるわけなんてないんだろうが。
要は、助けてと乞えてしまったのだろう。
同情とは違う、彼女のまるで自分のことのように痛み、心配する顔に、ただただ助けてとしか言えなかったのだろう。
助けなんて乞うつもりがなかったとしても。
「ほんと、へし折ったり噛み千切らなくてよかったよ。お前と会ったのは若干不服だけど。俺は、伸ばすべくして、由紀とお前の手を取ったんだ。きっとな」
だから、後悔もないし、これでいい。これでよかったんだ。
そう言って、やっぱり彼は清々しく笑った。
どうでもよかったと言いながら、これでよかったと言い、挙句運命だったと言って笑ってしまえる彼をほんの少し、うらやましいと思った。
きっと、それは、それだけ何も期待していなかったことの裏返しだ。
彼は何も期待していなかった。
手を伸ばす先なんて。
だからこそ、由紀と俺がその先にいたのは奇跡だったのだろう。
奇跡が信じられれば、運命も信じられるのかもしれない。
少なくてもそれは、俺にはできない芸当だった。
何も期待をしてないと自負する俺だったが、こいつほどではなかったなと目の前の男を見ながら思う。
何も期待をしていなければ、こんなに清々しく笑えるものなんだなと晴れ渡る晴天よりも眩しい彼の笑顔に俺は目を細めることしかできなかった。
※こちらは<#手を伸ばす先なんてどうでもよかったの続きをみんながどう書くのか見てみたい>というツイッターでのタグにて書いたものです。
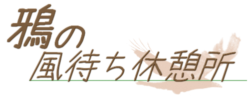


コメント