「クラン様」
そう、声を掛けられて、一瞬、自分が呼ばれているのだとということに気づけなかった。
「はい……。なんでしょうか」
と答えつつも、どうしても自分の名であるという認識が持てなかった。
それもそのはず。
それは、私の名ではなく、私の主人の名だからだ。
「そろそろ行きますよ」
自分をお嬢様かのようにそう告げるこの人は、私の上司であり、本来の“クラン様”の従者であるティール様だ。
「えぇ。そうですね」
重苦しいドレスに身を包み、精一杯笑顔を作る。
今日は、聖剣士家と聖剣士家の配下の家が集まる会合だ。
私が仕える聖剣士家サンチェス家は、現在、当主が病床に伏し、若き次期当主であるクランが会合に顔を出さねばならなかった。
しかし、それは、若き次期当主を大勢の前に晒すことであり、聖剣士家を純粋に支持していない家の者達の前に彼女を晒すことでもあった。
それはつまり、言ってしまえば、彼女の命を危険に晒す行為であった。
そのため、それを良しとしない今は亡きクラン様の父の命令により、影武者を会合に仕向けるということになっていたのだ。
そして、その影武者が私であり、それを支えるのが、本来の“クラン様”の従者であるティール様であった。
「ティール様も、本当のお嬢様じゃない私に仕えなきゃいけないなんて、大変ですね」
仕事の上司であり、仲間である彼に取るいつもの態度で彼に告げる。心からの感想だった。
「クラン様。私には何を言っているのか、よく分かりませんが」
などと、さも私がクラン様であり、言っている意味が分からないと白を切られる。
いいからクラン様として振舞っていろという圧を感じたので、それ以上は何も言えなかった。
「はぁ……。気が重いわ」
窓の外を見る。
窓の外は真っ青な晴天で、あまりに綺麗なので、余計に腹が立った。
いつもだったら、今頃、お嬢様を追いかけているところだろうな……といつもクラン様と過ごす日々を思い出し、早く、彼女の元に戻りたいと思う。
私の大切な大切なお嬢様だ。
まぁ、今は私がお嬢様なわけだが。
言っていて頭が痛くなってきた。
「あぁ。それから」
ティール様が私の顔を覗き込む。
私の身長はかなり低いだろうに、この人、良くこんなに顔を覗き込めるものだ。
「私のことは、ティールとお呼びくださいね。“クラン様”」
と強く、お前は“クラン様”なんだぞと釘を刺される。
いつも気さくに話をする間柄の彼と距離を感じて、やっぱり少し腹が立った。
「わかってるわ、ティール」
私も強めの口調でティールと呼んでやる。
そしたら、あっちは苦虫をつぶしたような顔をしていた。
これはこれでちょっと面白いな、いつか、いたずらするときに使おう。などと心の中で思う。
「それでは、まもなく会合の時間です。会場へ行きましょうか」
彼が差し出す手に自分の手を載せる。
これじゃ、本当に私がお嬢様みたいね。
普段はツーサイドアップにまとめている髪が今日はお嬢様の髪型であるツインテールに結われているので、二つにまとめた髪が私の肩を撫でる。
それが、あまりにも普段と違うので、改めて、今、自分はお嬢様になっているのだということを嫌でも自覚せざるを得なかった。
ティールに連れられ、会場までの廊下を歩く。
途中で、配下の家の者達とすれ違う。
「あら。今回もいらしゃったわ。サンチェスの幼子が」
「ローレイ様は病床に伏してると言われているけれど、実際のところ、どうなのかしらね。こんな小さい子を会合によこすくらい体調がすぐれないのかしら」
「こんな小さい子が会合に来て話を理解なんてできるのかしら」
などとこそこそ声が聞こえる。
私達は聖剣士家サンチェス家。
聖剣士家は代々血縁により聖剣が受け継がれている家だ。
たとえ、当主がいなくなったところで、その血縁を持つ者がいる限り、聖剣士家は途切れることはない。
逆にいえば、血縁が途絶えてしまえば、聖剣士家はそれでおしまいだ。
下々の者達が聖剣士家に取り入ろうと、聖剣士家を乗っ取ろうと画策しようと、聖剣士家の血を継がぬ者達が何をしたところで意味がないのだ。本当は。
しかし、それはサンチェス家の者とサンチェスに仕える一部の者しか知らない事実だ。
だから、聖剣士家の者の命を狙い、自分達がその地位を獲得しようと考えている者がいないわけではない。
故に、クラン様の父親であるフリック様はお嬢様の命を危険に晒すことはしたくなく、私のような影武者を立てたのだ。
私の本当の名はシエラ。
フリック様にもらった名だ。
私はサンチェス家領のそばに捨てられていた名もなき卑しい捨て子。
たまたまお嬢様と同じ目と髪色をしてたが故にサンチェス家に育てられた子供。
何の地位も価値もない子供だ。
フリック様は私にこんな命の危険に晒される行為をさせてすまないと言っていたらしいが、謝られるほどの価値が私にあるわけないことも私は知っていた。
所詮は、使い捨ての駒なのだ。
それでも、お嬢様の命を守れるのであれば私はそれで構わないと思った。
どんなことがあっても、それだけで前を向けた。
「本当に、馬鹿よね」
ふいに言葉が口からこぼれ出た。
「クラン様!?」
ティール様がとっても驚いている。
それもそのはず。
今、私は陰口をたたいていた人達の近くにいたのだ。
自分ってば馬鹿だなと思ってこぼした言葉だったが、これじゃあ、その人達に向けているみたいな言い方になってしまっていた。
違うけど、まぁ、いっか。
「あら。口が滑ったわ。なんでもありませんわ」
と、にっこり陰口をたたいていた人間たちに言う。
これは一種の牽制だし、事実、お嬢様やお嬢様の母であるローレイ様の陰口を叩かれていることには腹が立ったので、しょうがない。
「まさか、聖剣士家に盾突くなんて馬鹿な真似をなさる家があるとは思いませんもの。ねぇ」
特にローレイ様の体調に言及した女はきつく睨んでおいた。
当主の体調に言及するなんて。まるで、体調次第じゃ聖剣士家を脅かそうと思っていたんじゃないかと思う口ぶりだったから。
「クラン様。あまり事を荒げませんように」
ティール様が嫌な汗をかいている。
これ以上事を荒げないでくれと顔に書いてあった。
ごめんなさい。だって、腹が立ったんですもの。
お嬢様も、お嬢様の母であるローレイ様も私にとってはとても大切な人だ。
それを脅かすような人間がいては困る。
彼女たちは、現状、サンチェスの末裔だ。
もし、ここでその命が途切れることがあれば、サンチェス家は滅んでしまう。
それじゃ、困るのだから。
「あまり、サンチェスを舐めないでいただけますか」
ティール様も最終的にはそう言って彼女たちを睨んでいたので、人のこと言えないでしょう、あなた。と思いつつも、会場への扉をくぐった。
がやがやと喧騒が響く。
すでにかなり多くの者が集まっていた。
会場の奥にとても高そうな装飾のされた椅子が4つ並んでいる。
それが何を示すものなのか、長年会合に顔を出している私にはわかった。
「サンチェス家当主代理 クラン・サンチェス様の到着です」
どこかからアナウンスが飛んでくる。
その瞬間、集まっていた人間達の視線がこちらを向いた。
何度も会合に来ているとはいえ、この光景はとても苦手だ。
「来たわ」
「サンチェスの幼子」
「クラン様だわ」
やっぱりここでもひそひそされるのね。
この光景を目の当たりにしているのが自分でよかったと思う。
お嬢様がこの光景に晒されたら、さぞ辛いだろう。
私が本人でなくてよかったと心から思う。
「やあ。来たね。クラン」
と奥の4つのうちの1つの椅子に腰かけた長身の方が私に手を振っている。
「アジェン様」
彼は、アジェン・ナーウィル。4つある聖剣士家のうちの1つ。ナーウィル家の当主であり、この世界から神族の侵略を抑えるべく立ち上がった組織“世界防衛機構エルピス”の総長である男。
何年も容姿が変わらず、不老不死じゃないかと世間をにぎわす、その人のことが私はあまり好きではなかった。
けれど、お嬢様をサンチェスの幼子だのと陰口を叩く連中よりはよっぽどマシだった。
彼の元へ近づく。
「お久しぶりです。アジェン様」
「また君は大きくなったね。元気そうで何よりだよ」
にっこりとその人は笑う。
まぁ、その言葉は嘘ではないのだろうな。
世界に4つしかない聖剣士家。そして、たった4人しかいない当主。
きっと、当主たちはそれぞれの当主たちのことを大切に思っているのだろう。
4人が全員聖剣を扱うという重い運命を背負った者達だから。
きっとどこか通じるものがあるのだ。
聖剣士家の血がつながっていない私にはわからないことだが。
彼に頭を下げる。彼の後ろに控えていた片目を髪で隠した橙色の短髪の青年もこくりと頭を下げていた。
彼はアジェン様の従者なのだろうか?
いつも会合で顔を合わせているのでもうすっかり顔なじみだ。
彼にも頭を下げ、私は二つ隣の席へ移動する。
そこがお嬢様、サンチェス家の席だ。
アジェン様の隣は本来グローモス家の椅子なのだが、現在そこに座る当主はいない。
グローモス家はすでに滅びて久しい。
聖剣士家が滅ぼされるとどうなるかという現実を表している。
一度その血が絶えてしまえば、二度と復活することはないのだと。
そんなことを想いながら、その席を通り過ぎた。
そして私の席の隣に座る男性も嬉しそうにこちらを見ている。
「クラン」
白髪の長髪をみつあみに編んで後ろに流す彼は、聖剣士家の一つエン家の当主フォール・エン。エン家とサンチェス家は近くに位置しているため、頻繁に顔を合わせる仲であるので、挨拶はそこそこだ。
彼の後ろには茶髪の青年が眉間にしわを寄せて難しそうな顔をしていた。
「フォール様もウィンタ様もごきげんよう」
と二人に頭を下げる。
茶髪の青年はエン家の次期当主ウィンタ様だ。
ウィンタ様は眉間にしわをよせ、じっと会場を見渡している。
私の挨拶にはこちらを見ずに頭を下げるだけだった。
ウィンタ様ってクラン様を前にした時とこういう場にいる時とでは全然雰囲気が違うんだよな。
今は、すごく殺気立ってる。
当主の警護も兼ねてついてきているので当たり前なんでしょうけど。
「クラン様」
ティール様が私に着席を促す。
私が座れば会合が始まるのだ。
私は会場を見渡し、一礼をして、席に着いた。
その瞬間、先ほどの喧騒が嘘かのようにしーんと会場が静まり返る。
これから始まるのは、聖剣士家の今後についての話し合いだ。
聖剣士家として君臨する3人。その後ろに控える、従者・次期当主。
そして、純粋に聖剣士家を支える家の者。ひそかに聖剣士家の座を狙う者。聖剣士家に取り入ろうと考える者。
いろんな思惑渦巻く会場を私はじっと見据えた。
***
がやがや。
数刻が経ち、会合は終わった。
会場から、ほとんどの者が出ていく。
聖剣士家以外の者が去るまで、私達聖剣士家の者は椅子に座り続けている。
早く、出ていかないかしら。
重苦しい緊張感がまだ続いている。
聖剣士家以外の者がここを去るまで気を抜けない。
「ところで、クラン。今日はとっても緊張していたようだね」
こっそりとアジェン様がこちらに声を掛けてくる。
「そうでしょうか。緊張しているのはいつもです」
務めて、平静を装うつもりだったが、思いのほか自分の声が震えていて、自分が思った以上に緊張していたことに気付く。
ふぅと深呼吸をして続ける。
「自分は幼い故、いつ命を狙われるか分かったものじゃありませんから」
毅然とした態度をしなくてはと思いつつ、どうしても一度自覚した緊張は簡単には解けなかった。
ぎぃと会場の扉が閉まる。
会場には聖剣士家3人と、それぞれの従者と次期当主だけが残された。
「さて。ここからはオフレコだけれど」
とアジェン様が切り出した。
「まずは、緊張を解いていいよ。“シエラ”」
自分の名を呼ばれて、びくりと肩が上がる。
そもそも、ここにいる人間は全員私が影武者であることを知っているのだから、彼がそういうのは当たり前なのだけど。
クランとして振舞っていたので、自分の名を呼ばれたことにびっくりした。
「お疲れ様。シエラ」
フォール様もそんなことを言う。
私はただの捨て子なのに、こんな人達に労われてていいのだろうか。
「い、いえ。本当のクラン様ではなく、申し訳ありません」
と頭を下げる。
全員が承知の上なので、謝ることではないけれど。
なんだか、すごく申し訳ない気分だ。
「そんな頭を下げなくていいよ。クランの代わりを君が務めてくれるから、僕達も安心できているのだから」
「そうだね。幼い彼女をいつ刺客が来るかわからない場に置くのはやはり怖いからね」
アジェン様もフォール様もうんうんと頷いている。
「ただでさえ、ローレイ様があの体調だ。いつどうなるかわからない手前、クランの命を危険に晒すわけにはいかないからね」
アジェン様はそう言って、私の頭に手を近づける。
「?」
「撫でてもいいかな?」
アジェン様がそんなことを聞いてきたので、構いませんが……と返す。
私を撫でることに意味があるのだろうか。
「クランの影武者を引き受けてくれ、今もその役目を果たしてくれてありがとう」
と優しく頭を撫でられる。
お父さんという存在がいたらこんな感じなのだろうか。捨て子の私にはわからないけれど。
ほんの少し、それを心地よいと思った。
「いえ、私なんかでお役に立てるなら、それだけで私は幸せです」
たとえ、お嬢様の代わりに殺されることがあったとしても、たぶん私は自分は幸せだというのだろうと思った。
私の幸せはあの優しくてかわいいお嬢様が生き続けることだから。
彼女を守るためなら命さえ惜しくない。
「君はとても、強い子だね。本当にありがとう」
アジェン様はゆっくりと私の頭から手を離す。
「シエラ、君は疲れただろうから、先に休みなさい。しっかり、ゆっくりと休むんだよ」
そう言って、私の退場を促す。
私の身を案じてくれているのもあるのだろうが、ここからは本当の当主様間のお話だから、私みたいな影武者はお呼びでないということなのだと察し、私は立ち上がる。
「分かりました。それでは、お言葉に甘え、先に上がらせていただきます。アジェン様、フォール様。そして、ウィンタ様と……えっと……」
そういえば、アジェン様のそばに控えている人の名を知らなかった。
私が言葉に詰まっていると、橙色の髪の彼は静かに「カイトとお呼びください」と言った。
「カイト様も。今日はありがとうございました。皆さまもどうかご自愛くださいませ」
スカートを持ち上げ、礼をする。
本来であれば、この程度の礼ではいけない立場だけど、今の私はお嬢様なので、そのくらいの礼で済まし、その場をあとにする。
私の後ろをティール様はついてきた。
会場の扉をティール様が開け、私とティール様はその場を後にした。
「疲れた」
とつぶやく。
私ではなく、ティール様の声だった。
「え? ティールが?」
と返すと、ティール様、やっぱり苦虫をつぶしたような顔をする。この人、私から呼び捨てされるのすごく嫌そうというか、変な気分なんでしょうね、きっと。
「そうだよ。お嬢様の警護だとしても疲れるけれど、君の警護はもっと疲れるんだ」
それ、どういう意味?
「君がめんどくさいとかそう言いたいわけじゃないからね。ただ、すごく疲れる」
「お互い、嘘をついているからじゃないですか? 私達、本来こんな関係じゃないですもの」
二つに結われた髪を私はほどく。
やめだやめだ。
会合が終わったのだから、お嬢様の髪型なんてまっぴらだ。
この髪型をするのはお嬢様だけでいい。
「確かに、君はクラン様の振りしてるより、いつも通りの方が僕は落ち着くよ」
「私も、ティール様にお嬢様への態度みたいなことされるのはやっぱりむず痒いです。向いてません」
お互い、やっぱりこんなの向いてないと愚痴を垂れながら控室へ戻る。
もう建物内には人は残っていなかったのでいいだろう。
風が私の髪をなびく。
ふわりと自分の髪が目に入った。
「やっぱり似てないと思うわ」
そうつぶやく私にティール様は首を傾げた。
「私の髪とお嬢様の髪よ。お嬢様の髪が小麦だとしたら、私の髪は藁ね、きっと」
「……」
ティール様がすごい面くらった顔をしているので、あまりにおかしくて、噴出した。
「あはは!! すごい顔! ティール様、すごい顔してますよ」
と茶化すと、ぽんと頭に手を置かれた。
「そういうことを言うのはやめろ」
そっぽ向きながらそう言われても、真意はわからない。
「小麦だろうが藁だろうが、変わりないだろう? そんな絶望したような顔でそういうこと言うのはやめてくれ」
……。
私、絶望してたのだろうか?
ティール様が感傷に浸りすぎなのでは?
と思う。
別に絶望なんかしていない。
ただ、嫌でも気づいてしまう。
私はお嬢様とは程遠い、ただの大した価値のない捨て子なのだと。
彼女の振りをするたびに思い知らされる。
私は彼女ではないのだと。
お嬢様の髪はとても綺麗で艶のある太陽の香りがする小麦色。それに対して、私の髪はくすんだ藁のような色だ。
背丈や髪色が似てるとは言っても、私達は違う存在なのだと嫌でも気づく。
ただそれだけ。
別に絶望なんてしてない。
ただ、いくらお嬢様の恰好をしても私は所詮捨て子なのだと気付いて、虚しいだけ。
「絶望なんてしてませんよ。ティール様、変なこと言わないでください」
「そう……」
ぐりぐりと頭を撫でられる。
何なの? 最近、私の頭を撫でるのが流行ってるの?
「確かに、クラン様と触り心地が違う」
ティール様がつぶやく。
「は?」
「シエラはシエラでいいんだよ。クラン様と一緒になる必要なんかない。君は君でいればいい」
ぐりぐりと頭を撫でられる。
いや、これ、撫でるっていうか、頭ぐわんぐわん揺らされてるだけでは……と頭の片隅で思いつつも、この人の頭の撫で方が嫌いじゃなかった私はそのままにさせておく。
アジェン様は本当に優しく撫でてくれたんだわ。まるで壊れそうなものに触れるように。
そういう意味では、やっぱりティール様の撫で方が嫌いじゃないなと思った。
この人は私をクラン様やその代わりじゃなくて、私として、シエラとして、こんな力強く頭を撫でてくれているいるのだと分かったから。
彼にとって、私は壊れ物ではないのね。
それがなんだか心地よかった。
「なんで、ティール様が泣きそうなんですか?」
ふと彼を見上げると泣きそうな顔をしている彼と目が合った。
「何でもない。君が変なことを言い出すからだろ。まったく」
ふふふと笑みをこぼす。
この人のこういうところ、嫌いじゃない。
「笑ってないで、さっさと着替えて来なさい。君はドレスより、いつもの服の方が似合う」
ティール様はそう言って私を控室に押し込む。
ちょっと乱暴だなと思ったけれど、私も早く着替えたかったし、彼のそういう態度は同じ職場で働く仲間としての扱いだと分かったので、許した。
彼に促されるまま、私はドレスを脱ぎ捨てて、いつもの制服に腕を通す。
私の仕事着。一張羅。メイド服。
私は正確には従者であり、メイドではないのだけど、お嬢様のそばにつくのに都合がいいということでメイド服を着ている。
いつもの私の服だ。
いつもの服に身を包み、髪をツーサイドアップに結びなおす。
鏡に映る私はすっかりシエラ・ロータエという名の少女に戻っていた。
ひざ丈のスカートに安心感を覚える。
やっぱり、私はこういう動きやすい服の方がいい。
あーあ。さっさとこんな場所から帰ろう。
お嬢様の待つサンチェス家へ。
「お待たせしました!」
いつもの服で控室を飛び出す。
ティール様は元に戻った私の姿に微笑む。
「やっぱり、君はそっちがいいよ」
「自分でもそう思います」
「だろうね」
さっきと全然顔が違うから。と彼は、いつも通り笑った。
やっぱり、この人もいつも通りの方がいい。
お嬢様のそばにいる彼も嫌いじゃないけれど、やっぱり、私達の間柄は上司と部下であり、同僚だ。
そういう気の置けない仲の方がいい。
「あーあ。早く私のお嬢様に会いたいなー」
私がぼやくと、ティール様はむぅと頬を膨らます。
そうそう、これこれ。
「君のじゃない。僕のお嬢様だ」
と、この人私より断然年上なのに張り合ってくる。
「えー。でも、ティール様、私よりお嬢様のそばにいないことの方が多いじゃないですかー」
「そんなことない! 何より、君たちが来る前は僕が一人でクラン様のそばにいたんだ。君より断然僕の方がクラン様と一緒にいる!」
「じゃあ、帰ったら、お嬢様に聞きましょう? どっちの方が好きですかーって」
「ばか。クラン様を困らせるんじゃない」
「あらあらー。そんなこと言って、私に負けるのが怖いんじゃないですか、ティール様」
「言ったな!?」
なんて、馬鹿な張り合いをひとしきりして、私は、笑った。
あー。楽しい。
「そういう顔してなよ。君のいろいろなことを理解してるつもりだけど、やっぱり、笑っている方がいいよ」
ティール様、やっぱり感傷に浸った顔をしている。
そんな顔しなくても大丈夫ですよ。
私、この生活には満足してますから。いろいろ大変なことはあれど。
「じゃあ、ティール様、これからもたくさん私のこと笑わせてくださいよ」
あなたくらいしか、まともに私のこと笑わせてくれる人いないんですから。
こういう馬鹿な張り合いをしてくれるのはあなたくらい。
あとは大好きなお嬢様くらいだ。
「善処するよ」
「そこは任せろって言ってくれません?」
「まったく、君は……。そうやって口が減らない方が君らしいよ」
「ですね」
彼と並びながら、サンチェス家への帰路に就く。
お嬢様は今日の会合のことなんて知らない。
置いてきたお嬢様とティール様の弟であるロッキー様は今頃どうしているだろう。
私達の帰りを待っているのだろうか。
早く帰りたい。
お嬢様の影武者なんてやっていても、私の心はお嬢様の従者だ。
早く帰って、彼女のそばに仕えるのが一番私らしい。
だって、私は、シエラ・ロータエ。
聖剣士家の1つ。サンチェス家のお嬢様、クラン・サンチェスの直属の従者兼影武者。
私が仕えるのはただ一人。クランお嬢様。彼女だけなのだから。
はやく、帰ろう。
先ほどの影武者ではなく、本当の私のお嬢様の元へ。
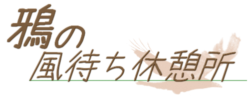

コメント