「死にたい」
ポツリと呟いて、苦しい……と胸を抑える。
呟いたところで無駄だと、分かって呟いてしまったことが、より一層苦しかった。
真っ白な空間に、投げ出された足を眺める。
ガリガリに痩せ細った足。栄養などとは無縁の生活を送った爪は脆く欠けていた。
ゴホッと咳き込む。
口の中に血の味が広がり、思わずそれを吐き出す。
口元を抑えた手が赤に染まる。
苦しい。
苦しい、苦しい、苦しい。
駆け上ってくる苦しさに、体を丸める。
苦しい。
苦しくて、寂しい。消えたい。死にたい。
そんな気持ちに僕は自分の体を抱きしめることしかできない。
体を抱きしめるように、縮こまった僕の眼下には血の赤とそれに塗れた汚らしい色の髪が飛び散っていた。
部屋を埋め尽くす白と、眼下の赤のコントラストが脳髄を刺す。
気持ち悪い。と思い、口元を覆う。
もう、時間の感覚がない。この場所にいつからいたのかも覚えていない。
ありとあらゆる実験に耐える時間だけが続いている。
それはもう気が狂いそうなほど長く。
もはや、何をされても恐ろしいと思えなくなってきている。
けれど、先ほどまで自分の体で行われたことを思い出すと、息が詰まる。
息を吸おうとした時には、もう、呼吸の仕方が分からなかった。
息ができないくらいで死ねたなら、苦しくないのに。
と呼吸の仕方を忘れた体を抱きしめて、目を閉じる。
暗い。
黒。
何も見えないその瞼の裏が今は無性に優しく思えた。
このまま、消えてしまえたら、どんなに幸せだろう。
そうならないことを僕は知っている。
僕は、逃げられない。
死ぬことができない。
死にたくないとか、死ぬのが怖いとかそういうことではない。
物理的に、死ねないのだと僕は知っている。
どんなに息を止めようが、切り刻まれようが、引き千切られようが、毒を飲もうが、僕は、死なない。
ありとあらゆる実験を施されたこの体には最初に負った左肩から脇腹にかけてついた大きな傷以外、傷の一つも残っていない。
肉体と呼べる何もかもが失われるような痛みを味わっても、しばらく経てば僕の体は元の体の形に戻っている。
苦しい。
苦しさに眩暈が、頭痛がする。
苦しい。苦しい。苦しい。
息ができない。
ここから消えたい。
どうにかなりそうだ。
というか、とうの昔にどうにかなっている。
その事実に僕はどうしても苦しくて、頭を掻き毟る。
髪の毛を引き千切るほど強く。皮膚から血が流れるほどきつく。
強く強く掻き毟った。
指の隙間から、髪が血が零れ落ちていく。
今の自分の容姿がどうなっているかなんて知らない。
ただ、指から零れ落ちるその色は知らない色だった。
黄色。緑。黒。赤。紫。
知らない。知らない。
僕の髪の色はこんなじゃなかった。
知らない色に塗れた手を見て、僕の口からは悲鳴が漏れていた。
おかしい。
何もかもおかしい。
僕は、いったい何にさせられようとしているんだ。
これが現実なのか、悪夢なのか、もう何も分からなかった。
実験のせいで中身なんかない、胃の中のものとどこから出ているのかもわからない血を吐き散らす。
何も分からない。
死にたい。
死にたい。死にたい。死にたい。死にたい。
死ねない。
死ねない。死ねない。死ねない。死ねない。
なんで。なんで。
自分の吐瀉物に塗れた自分の体だけを抱きしめて、僕は、虚空を見つめた。
真っ白で窓もない空間。
助けてなんて言わない。
だって、神様なんていない。
神様なんて奴がいるとしたら、そいつはきっと凶悪で醜い顔をした科学者に決まっている。
クソだ。
ゴホッと吐ききれなかった何かが口に溢れる。
それを吐き捨てた。
「――――」
助けを乞うこともできない僕の口からは何の言葉も出ない。
苦しい。
悲しい。
辛い。
怖い。
悔しい。
消えたい。
逃げたい。
生きていたくない。
死にたい。
それでも死にたくない。生きていたい。
何も出てこなかった。
代わりに涙が零れ落ちた。
自分の涙が何色をしているのかもわからない。
呟く言葉を失った僕は、それでも、何かを言いたくて口を動かす。
零れた言葉は、何のことはない言葉で、だからこそ空しさに心が痛かった。
「――――か、ぁさん」
「たすけて」
神に乞えない僕は、母さん、と赤子のように泣いていた。
こんな思いをするくらいなら、あの胎の中に帰りたい。
そう思った。
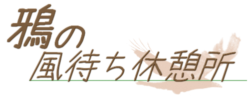

コメント