「子供が生まれたんだよ」
赤い髪を左肩に流すように結んだ男の人、僕の親戚筋の男で、今は主人と言っていいその人は内緒話でもするような声音で僕にそう言った。
「こ、ども」
齢10の僕は、その言葉を噛みしめる。
自分には8つほど年が離れた弟がいるので、あぁ、赤ちゃん、と納得する。
「おいで」
男の人に手招きされ、部屋に案内される。
人一人が生活するには十分な大きな部屋の中心にポツリとゆりかごが置かれている。
小さな小さな命。
覗き込んだゆりかごの中にいた生まれたばかりの赤子は、しわしわで、内心、あまり可愛くないな、と思った。
「可愛いだろう?」
と男の人に問われる。
「うん……」
そうだねと心にもないことを答えながら、しわしわで目も開いていないその小さな塊をじぃっと見つめた。
「名前は?」
男の人を見上げ、問う。
これまた内緒だよと言うように、彼は微笑んだ。
「クラン。クランだよ」
「クラン」
クランと口の中で音が転がる。
かわいらしい音だなと思う。性別は確か女の子だと聞いていた。
髪の毛も生えてなくて、目も開かずすやすやと寝ている目の前の赤子を見つめる。
これが、僕のご主人様。
小さくてどこかに力を入れて握りしめてしまえば壊れてしまいそうなその小さな命が、僕のご主人様になった日のことだった。
***
「元気にしてるかい? ティール」
剣の稽古が終わり、水道で顔を洗っていると後ろから不意に声をかけられた。
赤い髪を左肩にかけて結ぶ、珍しい青い目を持つその人は、このあたりでは聖剣士家と呼ばれ、権力を持つサンチェス家に婿として入った親戚筋の男で、今は名目上主人となっている男だった。
「フリック様」
その名を呼ぶ。
主たるその人を様付で呼ぶことはこの地域では至極自然なことだった。
「元気です」
「ならよかった。折り入って、ウェンテスタ家に……というか、君にお願いがあって来たんだよ」
ウェンテスタというのは、僕の苗字だ。
聖剣士家であるサンチェス家とエン家直属の騎士及び従者を排出する一家である。そして、僕もその一人として育成されている現当主の嫡男であった。
「僕、ですか」
ウェンテスタの名をいずれ継ぐことになる僕に、直接、主たる家の男が訪ねてくること自体はおかしいことではなかったのだが、まだ10歳になったばかりの僕のところにお願いというのも不思議なことだな、と僕は問いに問いで返す。
「一応、お父様方にはすでに話は通して来ていてね。詳しい話は君と直接してくれとのことだったんだけど、今、時間はあるかい?」
父に話が通っているというのであれば、それを断る理由もなく、僕は彼の言葉に頷いた。
「簡単に言うと、君には近々、サンチェス家で働いてもらいたい」
「……」
要するに僕をサンチェスの従者として迎え入れたいのだろうことは分かる。
だけれど、僕はまだ10歳になったばかりで、従者としても騎士としても配属されるにはまだまだ力量不足ではないかと思えてならなかった。
となれば、検討が付くのは見習いとして、だろうか。
「見習い、ですか?」
「いや、正式にだよ」
「僕、ですか?」
正式にだというその人に、改めて同じ質問を返してしまう。
騎士見習い、あるいは従者見習いならまだ分かる。
それを正式に、つまるところ、見習いをすっ飛ばして一人前にされるということだ。
僕は面食らった。
「とはいっても、もちろん勝手が分からない部分もあるだろうから、見習いのような仕事はしてもらう。それでも、何より、信頼のおける君にしか頼めない仕事だからだよ」
「信頼」
フリック様の言葉を噛む。
聖剣士家が権力を持つこの地域は権力争いが絶えない。正確には、聖剣士家の下につくウェンテスタを含めた下々の争いだ。
如何にサンチェス家、エン家に取り入るかと言うことを考えている者達にあふれかえっている。
直属の地位を与えられているウェンテスタと言え、その争いと無縁ということはない。
けれど、長年この地位を確立している我が家は、聖剣士家にとって唯一信頼を得ている存在であることもまた事実だった。
そして、幼い子供であれば権力争いと関わっていることもない。
だから、信頼を重視した結果、僕に白羽の矢が当たったということなのだろう。
「それで、その仕事って、なんですか」
緊張で喉が渇く。
それほど信頼が重視される仕事である以上、生易しい仕事でないことは子供ながらに分かった。
だからこそ、酷くそれを聞くのが怖かった。
「今度生まれる僕の娘の従者になってほしい」
まるでプロポーズのような文言でその人は言った。
***
クラン。
それが、サンチェス家に生まれた長女の名前だった。
そして、今、ゆりかごの中にいる小さな僕のご主人様だった。
「クラン、さま」
小さな小さな命に手を伸ばす。
壊れてしまいそうだなと思った手前、どうしても触れようとする手が震える。
「怖いかい?」
フリック様が僕の横にしゃがみこんで聞いてくる。
僕は素直に頷いた。
「怖い。壊れてしまいそうだから」
そして、消えてしまいそうだと思った。
サンチェス家は代々女性が継ぐ。しかし、なぜかこの家の当主は短命だった。事実、クラン様の母親でフリック様の妻であるところの現当主ローレイ・サンチェス様もまた体が弱く、長くは持たないだろうと言われている。現に、生まれたばかりの赤子をこんな広い部屋において病床に伏していた。
だからこそ、なお、この目の前の命が怖かった。
そして、この子の世話を任された自分の使命もまた怖かった。
震える手は結局、赤子に触れることなく、自分の胸の前に戻る。
その手をもう片方の手で握りしめ、僕はゆっくり息を吐いた。
その様子を見たからか、フリック様が僕の背を擦る。
「大丈夫だよ。怖いのも今のうちだよ。きっと、この子は元気に君を困らせるに決まってる。だから、そんなに怖がらなくても大丈夫」
そう言うこの人の手も震えている。
生まれたばかりの赤子を前に、命の先輩にあたる自分たちはなぜこんなにも震えているのだろうと思う。
それでも、僕とフリック様は震えていて。
命のありがたさよりも、恐ろしさを知った日だった。
***
あれから、5年の月日が経過していた。
僕も少年と呼ぶには、だいぶ年を重ねたように思う。
けれど、彼女の命に震えていた日は昨日のように思い出せる。
そして、あの日、僕の背を震えるように触れていたあの人の体温も昨日のように思い出せる。
結局、あの夜、クラン様に触れることはできなかった。
怖くて、怖くて、震える手を差し出せるほどの勇気はまだ幼い頃の僕にはなかった。
けれどそうも言っていられなくなった。
フリック様が戦中に亡くなり、ローレイ様もクラン様のそばにいることは叶わず、当主の夫が亡くなったことを狙うように下々の争いは増した。
怖いなどと言っている暇が無くなってしまった。
クラン様を、自分以外の誰も守れない状況に気が付けばなっていた。
結果的に、僕はフリック様の思惑が当たったことを思い知らされた。
あの人は、自分がいなくなる可能性を、ローレイ様がクランの母親として彼女を育てることが難しくなることを分かっていた。
かといって、乳母や女中だけにことを任せるのは恐ろしかったのだろう。思惑渦巻くこの街で、確実に味方になり得る人物をあの人はクラン様のそばにつけておきたかった。
それが僕だった。
確実に信頼できる、世俗に塗れる前の年端もいかない少年。
あの人が求めたのはそういう人で。
たまたまウィンテスタ家の長男に生まれ、たまたま彼女が生まれる前にあの年齢だっただけのことで。
それでも、もしあと数年遅ければ、僕が彼女のそばにいることはなかった。
今となっては、彼女のそばにいるのが自分でよかったと心から思う。
赤子の頃から、彼女の成長を見守り続けた日々は決して楽ではなかったけれど、この小さなご主人様と過ごす毎日は不幸ではなかった。
「ティール」
可愛い声が足元で僕を呼ぶ。
自分で言うのもなんだが、あの日、可愛くないなどと思った赤子は恐ろしく美しい少女になっていた。
それはそれは国を傾けられそうな美少女だった。
「なんですか、クラン様」
その声に彼女を見下ろす。
あの日しわしわだった顔は柔らかなシルクのような肌に。その頬には柔らかな赤を宿している。
あの日は生えていなかった髪は彼女の母親譲りの綺麗な小麦色で。肩にかかるその髪はくすぐったそうに彼女の肩を撫でている。
あの日見ることができなかった瞳は彼女の父親に良く似た青色をしていた。水面のように澄み渡る青い瞳。
かつて、僕にこの日々を仕事として与え、今はいなくなった男の人と良く似た目が僕を見る。
「何でもない。呼んでみただけ」
うふふと少女は嬉しそうに笑って僕の足にしがみつく。
何のことはない。
恐ろしいと思っていた命はとても強かに生きていた。
父が亡くなり、母は病床に伏し、彼女自身はかわいそうだと哀れまれていても、ありとあらゆる人間の暗い思惑が自分の周りに渦巻いていようと、僕の足元で幸せそうに微笑んでいる。
彼女は僕があの日思ったよりもずっとずっと強い女の子だった。
足にしがみつかせておくのはあまり抱き心地も良くないだろうと僕は彼女を抱き上げる。
ぐっと腕にのしかかる重みは、あの日壊れそうだったものとは思えないほど、確かな重みを持っていて。
抱えた腕から彼女の体温が伝わってくる。
とくとくと鼓動の音が聞こえる。
抱き上げた彼女は、全身から生きていることを主張している。
あぁ、生きている。
僕のご主人様は元気に生きている。
亡くなる命があっても、消えそうになる命があっても、人を騙し我先にと心無い命があっても。
このご主人様はちゃんと元気に幸せそうに生きている。
それが酷く、嬉しいと思った。
自分が生きていることよりも嬉しいと思った。
「ティール?」
「なんですか。クラン様」
「泣きそう?」
小さな女の子から頬に手を伸ばされる。
ぺたりと小さな手が僕の頬に触れる。
温かい。
あの日、壊れそうだと触れられなかった彼女は、こんなにも簡単に僕に触れてくる。
今この瞬間は、生きていることがとても嬉しいと思えた。
「クラン様」
その名を呼ぶ。
「なぁに。ティール」
へにゃりと微笑むその顔が微笑ましくて。
僕は彼女を抱き上げた手とは逆の手を使って、彼女の頭を優しくなでる。
ふんわり揺れる柔らかい髪をくすぐったそうに彼女は笑った。
生きている。
あの日恐れた命に触れて、実感する。
そして、彼女が生きていることが心から嬉しかった。
あの日、怖いと思った命を心からありがたいと思った。
たとえ、いつか彼女のそばにいれなくなっても、彼女がいなくなる時が来るとしても。
その日までは、このご主人様のそばにいようと思う。
だって、彼女が生きていると嬉しくて、僕も生きていることがこんなにも嬉しいのだから。
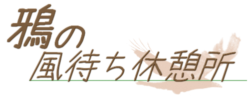

コメント