「どうして行ったの?」
俺の問いに答える声はない。
「あれほど行くなって……。 俺は何度も言ったのに……。どうして聞いてくれなかったの。ハリス」
心の中は怒りでいっぱいだった。
どうして……。
いつも君はそう。 どうして、僕の言うことを聞いてくれない。
「自業自得だよ……」
答えはやっぱりかえってこない。
「お前は馬鹿だ。大馬鹿だ! なんで、言った通り学校にいなかった。俺は、知ってたんだ……。こうなるのを知ってたから、行くなって言ったんだ!」
どんなに怒鳴りつけたところで、背中のハリスは動かない
「……そんなに、あのナーウィルの野郎が好きだったのかよ……。あの女に惑わされたあいつをそんなに好きでいる必要がどこにある……。 あいつを追いかけて……。自分がこんな目に遭ってどうする!! だから……。言ったのに……。」
どんなに叫んでも答えない背中の”彼”に俺は泣き始めてしまった。
全く自分でも自分が情けなくなってくる。 そう、知っていたんだ……。
知っていたのに、俺が目を離したのが悪いんだ……。そんなの分かっているんだ。それでも、どうしても泣かずにはいられなかった
「バ……ばかは、どっち……?フィーンド」
耳元で聞きなれた声が俺を呼ぶ。
「は、ハリス!?」
俺は思わず、”彼”を背から落としてしまいそうになる。
「痛ッ……。慌てすぎ……。」
「生きて……!?」
「…………か、勝手に。……殺さないでくれる?
と、とりあえず、おろしてくれないかな……。」
弱々しい声。
俺は慎重にハリスを背からおろし、坐らせてやると向き合った。
「……眉間にしわ……。怒ってる……?」
こんな状況でも、“彼”は恨み言1つ漏らさず、俺にそう言った。
「馬鹿か!!お前!!これのどこが怒らないでいれる!!ふざけんなよ……ほんと……。」
あぁ。そこまで怒鳴っておきながら、泣きだしたのはやっぱり俺の方だった。
「泣き虫。君は横暴で、強がりで、融通が利かなくて……。 優しいんだか、そうじゃないんだか……」
ハリスはそういって目を瞑る。
「君はさ、もっと優しいんだから、僕じゃない人のところに行きな……。 僕は、知っての通り馬鹿なんだ。君のいうことも聞かなくて、こんな目に遭って。それでも、まだ嫌いじゃないんだ……。馬鹿だろ?」
まるで、自分なんか忘れてくれとでも言いたげな口調に、俺は何も言えなくなってしまった。
ただ、その時になって、初めて俺は気づいてしまった。
……こいつが馬鹿である以上に、俺はこいつのことが好きだったのだと……。 分かってしまった途端、俺の中には絶望と悲しみだけが広がっていた。
ごめん、ハリス……。 それでも、俺はそんな馬鹿な君が大好きだったんだ――――。
悪魔と少年の話
 Divine
Divine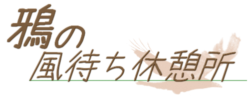
コメント