ザァ……
雨。雨だ。
窓を眺めるまでもなく、雨だ。
天井を仰ぐ。
今夜は、星は見えないだろうか……。
そして、雨の日は。
あいつが嫌いな日だ。
***
ガヤガヤ
たくさんの人間が声を発するあまり、人の声として認識できない音と、その合間を縫うようにカチャンと食器がぶつかる音がうるさい。
食堂と言えばそんなもんなんだろうが、雨の日はそれがやけに鬱陶しい。
あーうるさい。
ガシガシと自分の頭を掻く。
そんなことをしてもうるささがまぎれるわけでもない。
「うわ……噂の忌み目じゃん」
うるさくて、人の声として認識できなかったはずなのに、そんな声だけがあまりにも鮮明に耳に飛び込んできて、自分でも驚く。
どこだ。
誰が言った。
「おい、馬鹿。ほっとけって。下手に口にするもんじゃねぇよ」
あたりを見回す。
誰だ。
「あぁ……、あの噂の」
ひそひそされているはずなのに、やたらその声が耳につく。
うるさい。うるさい。うるさい……。
「サラ……?」
!?
うるさくて仕方がなかった声に紛れて……
いや、ひと際はっきりとその声が聞こえて、思わず振り返る。
何でだ?
お前、部屋から出ないんじゃなかったのか?
振り返った先の人物を見る前にその疑問が頭をよぎる。
「お前……」
振り返った先には、青い髪の少年が立っていた。
あれ?
お前……
「おい……あれって。青髪の化け物……!?」
「はぁ? あいつ、あんなに髪短くないんじゃ……いや、でも……確かに……」
あたしが口に出すより先に回りのやかましい人間たちの方がそれに驚いているようだった。
「おはよう。サラ」
今まで、はっきりとまともに見たことはなく、けれど、確かに知っているその顔がにっこりと笑う。
「お前……、カーラ、か?」
「ん? あぁ、そっか。そうだね」
真っ青な長髪に覆われていたはずの顔がはっきりと見える。
照れくさそうに短くなった自分の髪をいじりながら、カーラは言う。
「サラに会いたくなって、来ちゃった」
ニコニコと。ニコニコと。
笑いながら、カーラは言う。
なんだ? 何か違和感が……。
なんか、変だ……。
「お前、ちょっと来い」
「え……!?」
戸惑うカーラの心境はほっておいて、カーラの手を掴む。
「え!? ちょっと待ってよ! 朝ごはんいいの!?」
「そんなの、どうでもいい!!」
待って!? なんで!?
そう言うカーラの言葉を振り払って、カーラを人通りが少ない廊下へ連れ出した。
「ねぇ、サラ。待ってって」
カーラが息を切らしている。
そんなに急いだつもりはなかったが、どうやら、あたしは思ったより急いでしまったらしい。
息を整えたいだろうと、カーラの手を放す。
「サラ、どう、したの……」
息を整えるカーラの顔はどこか青白い。
あぁ、そうだった。こいつ、雨の日は体調が悪いんだった。
にも拘らず、変に連れまわしてしまった。
「悪い」
「いや、いい、けど……」
ぜぇぜぇとカーラの肩が揺れてる。
どっか、座れる場所はなかっただろうか。
「おや、お困りのようですね」
あたりを見渡そうとした瞬間に後ろから声を掛けられて、肩が飛び上がる。
いや、その声には聞き覚えがある。
そもそも、あたしに声を掛ける人間なんて限られている。
「隻眼郵便配達人」
振り返ってその名を呼ぶと
「はい。そうですよ」
と彼は嬉しそうに笑った。
「ずいぶん、焦ってますね。どうしました? それに……君は……」
隻眼郵便配達人はカーラの方を不思議そうに見ている。
「こいつは……」
「あぁ、知ってますよ。カーラ君ですね。でも……、君、どうして……」
あたしがカーラについて説明するよりも早く、隻眼郵便配達人はカーラのことがわかっていたようだった。
「うるさいな……。どうだっていいだろ」
吐き捨てるようにカーラが言う。その目は隻眼郵便配達人を睨んでいるようだった。
「そう邪険にしないでください。あくまでも僕は親切心であなたたちに声を掛けたんですよ。知ってるでしょう?」
睨むカーラに微笑みかける隻眼郵便配達人。
言葉のない睨み合いの間に挟まれて、居心地が悪い。
カーラも心配だし、隻眼郵便配達人のしたいことが見えない。
あたしが心配そうに二人を交互に見てたせいか、隻眼郵便配達人があたしの頭を撫でる。
「サラに触るな」
カーラがびっくりするほど怒気の含んだ声で言う。
カーラ?
「ふむ……。とりあえず、休憩室でお話ししましょう? カーラ君もそんな状態じゃまともに会話もできないでしょうし」
と、相変わらずの笑顔で隻眼郵便配達人は提案するのだった。
***
休憩室が近くにあると隻眼郵便配達人に案内される。
あたしとカーラの対面に隻眼郵便配達人が座る形で休憩室の机につく。
カーラはこの間、ずっとあたしの手を握りっぱなしだった。
まるで、怖いとでもすがってくるように。
そして、今もその手を放そうとしない。
「おい。カーラ」
もう、手放してもいいんじゃないか? と促すも、ごめんと返されるだけだ。
しょうがない。このままにしとこう。
「カーラ。お前、とりあえず、落ち着け」
ぜぇぜぇと喉を鳴らしているのをまず何とかしてほしい。
見てて、心配になる。
気が付けば、けほけほと咳までしてる。
「カーラ。ちょっと手放せ」
背中さすったほうが楽になるんじゃ? と思った故の提案だったのだがぶんぶんと首を横に振られる。
ダメか。
仕方がないので、握られた右手と反対の手でカーラの背をさすろうとしたが、一瞬びくっとカーラの肩が揺れた気がして手を止める。
そういえば、今まで髪に隠れて気付かなかったが、あまりに無防備な背中だなと思った。
「触らない方がいいか?」
と一応、カーラに聞いてみる。
また首を横に振られたので、おそらく、触ってもよいのだろう。
そっとカーラの背に触れる。
……ガリガリだな。
それもそっか。とつい先日までのカーラを思い出せば、それもそうだなと思う。
あんなんじゃまともに食事ができていたはずがない。
しばらく背をさすっているとようやく落ち着いてきたらしい。
「落ち着いたか?」
「ん」
あたしの問いに小さくうなずく。
うなずきながらもカーラの視線は隻眼郵便配達人に向いている。
しかもこれ、やっぱり睨んでるな。
「久しぶりに顔が見れたと思ったら、ここまで嫌われているとは思いませんでしたよ。カーラ君。一体、どういう心境の変化で?」
隻眼郵便配達人は睨まれながらも笑顔を崩すつもりはないらしい。
それに彼の関心はカーラの変化についてなようだ。
あたしもそれが気になって、カーラを連れ出したんだ。
「あんたには関係ないだろ」
相変わらず、カーラは隻眼郵便配達人を邪険にしている。
「カーラ。隻眼郵便配達人のことはいいけど、あたしも気になってるんだ。お前、部屋から出たがらなかっただろう? なんで外に……。それに、その髪、一体……」
つい先日まで、カーラは全く部屋から出ようとしなかった。
というのも、出ても「化け物だ」「無限に使える盾だ」などと言われて、いい思いをしないからで。
ただ戦場に駆り出されるか部屋にいるかどちらかだったはず。
戦場で生きたまま盾として使われるこいつは、心身ともに疲弊していて、自分の身なりなんてどうでもいいと言わんばかりに髪を伸ばしっぱなしにし、それ以外の身なりもかなり適当だった。
それが、だ。
今朝になって、絶対に出たがらなかった部屋から出て、食堂に来た上に、髪は肩にかからないくらいに切られているし、身なりはとても綺麗だ。
まるで、先日とは別人かのように。
誰もがどうして? と疑問を口に出すのは当たり前だ。
「さっきも、言ったけど。俺、サラに会いたかったんだよ。理由なんてそれだけ」
かたくなに放さない手が一層強く握られる。
嘘をついてるわけじゃなさそうだが……。
どうしても気になるのは、カーラの顔だ。
お前……、何で笑ってるんだ?
すごく胸がざわつく。
お前、そんな顔をしてたか……?
「ふむ……。そうですか。僕はてっきり……」
隻眼郵便配達人が何かを言いかけたが、カーラがあまりに睨みつけるので、その言葉は最後まで発せられない。
「あぁ……。余計なお世話でしたね」
そう言って、隻眼郵便配達人は、あたしを見る。
「サラさん。先ほど廊下で会ったの、偶然ではないんですよ」
「え?」
「僕はあなたを探していたんです。届け物があったので」
「届け物?」
あたしに?
天涯孤独の自分の身に届けられるものがあるとは到底思えない。
なのに、届け物? あたし宛に?
「届け物というと訝しまれるかもしれませんけど、言い方を変えましょうか。贈り物があったんです」
「おくり、もの……」
届け物より縁遠いものになった気がする。
届け物よりも一層あたしに縁がないもののはずだが……。
「あれ……。むしろ困惑させました? 難しく考えなくていいですよ。あなたに贈り物をしたかったのは、僕なので」
隻眼郵便配達人がそういうと、ぎちっと音が鳴りそうなくらいカーラが握っている手に力を込めてくる。
「カーラ……痛い」
カーラの握ってる手をちょっとだけ振る。
少し力を緩めてほしい。
ただでさえ、右は利き手なんだ。
「ごめん」
カーラは小さくつぶやいて、力を緩めてくれた。
「で、なんだったっけ。贈り物?」
「サラさん、今日、何の日かお忘れですか?」
「何の日?」
今日……。
今日、今日……。
七月三日……。
七、がつ、三、か?
「たんじょうび……」
久しく発していないその言葉に、一瞬頭痛が走る。
そんなものがあったことを、すっかり忘れていた。
「こちらにいらしてから、何度目かのお誕生日のはずですが、そういえば贈り物をされたことがなかったのではないかと思いまして。僭越ながら、僕の方で用意させていただきました。と言っても、そんなに大したものではないので、気軽に受け取ってください。アジェン総長曰く、日頃のボーナスとのことです」
そう言って、隻眼郵便配達人は小堤をあたしの前に置く。
「たんじょうび、プレゼント……」
すごく複雑だ。
最後に誕生日を祝われたのは一体いつだっただろうか。
何も思い出せない。
自分では祝っていたはずなのに、なぜか今日はすっかり忘れていた。
生きるのが、あまりに当たり前になっていたから……。
それでも、置かれたプレゼントに涙が出そうになる。
「ありがとうございます」
泣きそうになる目を左手で抑える。
泣くなんて恥ずかしい。
「いえ。あなたも日々、大変活躍されていると聞いてますので、ささやかなプレゼントだと思ってください。むしろ、このようなことしかできず申し訳ないくらいです。それに……カーラ君にとってはあまり面白くなかったようですから」
ん?
カーラにとっては面白くない?
カーラの方を見ると、口は笑っているけど、どこか不機嫌そうだ。
「ですから言ったんです。余計なお世話でしたね。と。でも、カーラ君。申し訳ないですが、これも僕の仕事なので、許してくださいね。まさか、君が外に出ているとは僕も思ってなかったんですから」
「いいよ。もう。いいからどっか行って」
隻眼郵便配達人の言葉にカーラはどうでもいいから、さっさとどっか行ってくれと相変わらず、邪険にしている。
「そうですね。お邪魔してしまったようですみません。それでは僕はこれで。サラさん。良きお誕生日を」
隻眼郵便配達人はそれだけを言うと去って行った。
最後に「カーラ君も」とつぶやいていたような気がするが、いったい何だったんだろう。
それにしても、そろっと手を放してくれないだろうか、カーラ。
「カーラ。手、もう、いいだろ」
「……」
「おい、カーラ?」
返事がないのでカーラの肩を揺さぶってみる。
「あ、ごめん。何?」
顔を上げたカーラは変わらず笑顔だ。
口だけは。
「お前……その顔どうしたんだよ」
「え? あぁ……これ……」
カーラは自分の頬に触れる。
「俺の顔、ちゃんと見たの初めてだっけ。俺、こんな顔なんだよね。自分でもすごく変な感じなんだ……」
そう言ってカーラはうつむく。
あたしとつないでいない右手で顔を覆う。
爪を立てていて、今にもひっかいてしまいそうに。
「おい、カーラ」
ひっかくなよとその手を掴む。
「あぁ、ごめん。俺も自分の顔が変で……気持ち悪くて。気付いたらひっかきまわしたくなっちゃって」
「それはやめろ」
「うん……」
やめろといったところでやめれないだろうな……と思う。
さっき食堂で会った時の違和感。
そしてずっとあたしの胸をざわつかせているこの感覚。
それは、カーラの心情と表情が全くあってないせいだ。
今まで顔が髪で隠れていてはっきりと見えなかったから気付かなかったが、カーラの顔にはずっと笑顔が張り付いている。
本人の意思、心情に反して。
もし、自分がそんな状態だったら、顔をひっかきまわしたくなってもおかしくないな……とは思う。
なおのこと、笑いたい気持ちなんて微塵もなさそうなカーラだ。
その気持ちはより強いのだろう。
ここまで我慢しているのがむしろ頑張っている方なんだろう。
「髪切ったんだな」
「あぁ……、うん。外に出るのに、あのままってわけにもいかないかなと思って」
「どうして、外に出ようと思ったんだ?」
「あぁ……えっと」
カーラは目を泳がせている。
髪で顔が隠れなくなった分、よりその様がよくわかる。
「カーラ?」
「あ、えっと。手、つなぎっぱなしでごめん。放す」
ぱっと右手が急に解放される。
あ……。急に放されるとなんだか、名残惜しく感じてしまう。
カーラの手、あったかかったんだな。
「えと……、何で外に出たか。だった、よね。あの、さ」
そう言ってカーラは小さな箱をあたしの前に差し出す。
「誕生日、おめでとうって言いたかったんだ。俺に用意できるものなんて、こんなものしかないけど、今日、サラに会って、これを渡したくて、ただそれだけだったんだ」
カーラに差し出されたものを受け取る。
小さな白い箱をそっと開けると、中にはオレンジ色のリボンが入っていた。
「こ、れ……」
「サラ、オレンジ色好きでしょ。だからさ、せっかくだし、こういうので髪結んだらいいんじゃないかなって思って……。本当は一番に祝いたかったんだ……。でも、隻眼郵便配達人に抜かれたし……」
後半は一人言なんだろうが、あたしの誕生日を一番に祝うために隠したかった顔を晒して、出たくない部屋の外に出て、来たくもない食堂まで出向き、あたしを探したってことなのか、こいつは……。
しかも、体調が悪くなる雨の日にも関わらず。
「お前、ばか、だろ」
あたしにこれを渡すために?
わざわざ出てこなくたって、あたしがお前の部屋に行くことくらいわかってたはずだ。
なのに……。
「サラ、俺ね。本当は、ずっと前に進まなきゃって思ってたんだ。でも、どうしても足が竦んでできなかった。今の状況なんて一生変わんないって。俺は一生生きた盾で化け物で、どんなに頑張ってもどうせいいように使われるだけなんだって思ってた。けど、俺とサラが出会ったあの日、サラ、言ったでしょ。『そんなに救ってほしいなら、あたしが救ってやる』って」
懐かしい言葉を耳にする。
こいつと初めて会った日。あまりにも死にたがってるこいつが許せなくて、酷くイラついて、こいつにこう叫んだ。
『そんなに救ってほしいなら、あたしが救ってやる』
正直、救ってやれるかどうかなんて全く考えてない、ただの口から出ただけの言葉だ。
それなのに、こいつはそれを覚えていたらしい。
「その言葉を聞いた時に思ったんだ。こんなに絶望しているのに、俺を救うなんて、何馬鹿なこと言ってるんだろうって。それと同時に思った。根拠もないのに救ってやるって叫ぶこの人はきっと俺を救えるって心のどこかで思ってるんだって」
カーラの言葉に返せる言葉はない。
たぶん、きっと、心のどこかでは思っていたんだ。
どんなに絶望的なこいつの状況でも、あたしは救えると。
根拠もないのに、なぜかそう思っていたんだ。
根拠もないんだから、理由なんてわからないが。
「こんな話をすると、サラは嫌かもしれないけど。サラはきっと忌み目って理由でずっとずっと、たぶん俺が知ってる絶望と同じ……いや、それ以上かもしれない絶望を味わったと思うんだ。それなのに、すごいよね。俺を救うってなんの疑問もなく断言できちゃうんだもん。サラは、未来を諦めてない人なんだってその時思ったんだ」
そう、なんだろうか。
あたしは根拠なく、ただ、こいつが死んでしまうくらいなら、あたしが救ってやればいいと、ただそう思っただけなんだ。
それでお前が死にたくなくなるならって。
だけど、そうなのかもしれない。
お前の未来も、あたしの未来も、たぶんあたしは諦められない。
例え、どんなに絶望で打ちひしがれても、折れなければなんとかなると思うんだ。
あたしが今エルピスにいるのが、それの何よりもの証拠だから。
「だから、俺。諦めるの、やめようって思うんだ。忌み目でも生きてきたサラがいるのに、俺が生きるの諦めてどうするんだって。救ってくれると言って、本当に俺から逃げないで俺に会いに来続けてくれたサラから、俺も逃げちゃだめだなって」
カーラは、まっすぐあたしを見据えている。
その顔はやっぱり笑顔が張り付いていたけど、唇が微かに震えていた。
そっか、それは笑顔じゃないんだな。
精一杯の強がりだ。
強がって、奥歯噛み締めて、頬引き摺らせて。精一杯強がった笑顔。
本当は外に出るのも怖かったはずで。
でも、そう悟られないように、ずっと口角を上げるしかなかったんだな。
「ねえ。サラ。俺と二人で……仲間が増えるならそれでもいいや。俺達でさ。てっぺん取らない?」
「てっぺん?」
急に何言い出すんだか。
唇震えてんぞ。
「忌み目だーとか、化け物だーとか。そんなの吹き飛ばしちゃうくらい強く強くなってさ。そんなの忘れさせちゃうくらい強くなろう。それでさ、誰もが当たり前に持ってる〝普通〟になろう」
〝普通〟。普通だっていうのに、それがあまりに特別に思えるのは、きっとあたし達二人そろって〝普通〟じゃないからだ。
あたしは不幸を呼ぶ〝忌み目〟の持ち主で。
こいつは死ぬことのできない不死身の〝化け物〟で。
でも、あたし達でも〝普通〟になれる。
強く、なれれば。
世界防衛機構エルピス。
ここでは実力がすべて。
実力があるものが正しい。
だったら、そうだ。
何もあたしたち、不遇に甘んじる必要なんてないんだ。
蔑まれ慣れて忘れていた。
この状況に甘んじなくていいのだという、当たり前すぎることを。
「サラ。前に一緒に星空見たの、覚えてる?」
「お前がやたら星が見たいって言ったあの日な」
部屋から出たくないカーラが、その日だけはやけに空を見たがっていたから、印象に残っている。
以降、夜に星が見えるか気になってしまうくらいに。
今朝だって、雨が降ってると気付いて最初に思ったのは星が見えるかどうかだった。
「その時は見えなかったけどさ。七月三日の誕生星っていうのがあるんだ」
「誕生星?」
聞いたことがない言葉に首をかしげる。
なんだそれは。
「誕生花とかって知ってる? 誕生日にちなんで花とか星とか石とか決まっててさ。それの星のことね」
「はぁ……?」
言ってる言葉の意味がよくわからないがとりあえず、聞く。
「七月三日の誕生星はね。タウ・プピス。冬に見える星座とも座の中にある星なんだって」
「カーラって、相変わらずよくわからない知識を持ってるよな」
「俺の家、本だけは豊富にあったからね」
「それで?」
話の続きを急かす。
「タウ・プピスにはこんな意味があるんだって。『強者と戦う強い意志』」
「強者と戦う強い意志」
「別にサラが弱者で他が強者だなんては言わないし、そうは思わないけど。なんだか、どんな相手にでも立ち向かえる気がしない?」
強者。弱者。
生きてる限り、淘汰されるものは弱者で、淘汰するものは強者だ。
でも、もし、その強者に向かって立ち向かえる強い意志が持てたら。
きっとそれは、誰にも負けない強さと言っていいはずだ。
「すごく、傲慢な言葉、だな」
「そう? でも、俺らにはそれくらいがちょうどいいんじゃない?」
「それもそうだな」
確かに、あたし達にはそのくらい傲慢な言葉がちょうどいい。
誰にだって負けてやらない。
何者にだって立ち向かってやる。
〝強者と戦う強い意志〟
そんな言葉が自分の中でキラキラ輝いている気がする。
まるで夜空に光る星のように。
「いい、言葉だな」
「そうだね。ちなみに、タウ・プピスって、オレンジ色の星なんだよ。ますます、サラに似合ってる」
カーラは私の手に載ったリボンを取ると、後ろ向いてと言う。
「せっかくだから、つけてあげる」
カーラの言葉に従って、後ろを向く。
カーラが手櫛であたしの髪をまとめていく。
両手とも手袋をつけているというのに器用なものだ。
「できたよ」
カーラの嬉しそうな声音にあたしは振り返る。
「鏡がないのが残念だな。似合ってるか?」
自分の姿を見るための鏡が休憩室にはなく、ただ朝食を取りに外に出ただけの自分が鏡を持っているはずもなく、現状あたしの姿を見れるカーラに問う。
リボンで髪をまとめた張本人に聞くのもどうなのかとは思うが。
「もちろん。やっぱり、サラはオレンジが似合うし、なんか、引き締まったって感じがしてかっこいいよ」
「かわいいじゃないのか?」
あたしの髪をまとめるため椅子に膝立ちしてたカーラを見上げる。
「え!? もちろん、かわいいよ!? そ、そうだよね! リボンをつけてるのにかっこいいは違うね!?」
あわあわと慌てるカーラが妙に面白い。
今まで見えなかった顔とか手ぶりが今ははっきりと見えるからだろうか。
「ま、いいや。似合ってるんだろ?」
見慣れないカーラの様子を見てると笑ってしまいそうになるので顔を背けながらカーラへ再度問う。
「もちろん!」
「じゃあ、いい。誕生日プレゼントありがとう」
嬉しいからか、恥ずかしいからか、顔が火照って来てる気がするので、そっぽを向いたまま、カーラに言う。
そしたら、カーラは嬉しそうに言うのだった。
「うん! 誕生日おめでとう。サラ」
***
しばらく他愛もない話をしてから、あたし達は食堂に戻ることにした。
気が付けば、朝食なんて時間は過ぎ去っており、昼食の時間になってしまっていた。
「結局、あたしに会いたかっただけなのか? 本当に?」
あたしは頭についたリボンをいじる。
これを渡すためだけにしては、髪や身なりを整えたり、一歩を踏み出す決心をしたりしたことを考えると凄い労力だったろうし、どうしてもそれだけではないような気がしたからだ。
「それは本当だよ。今日はサラの誕生日だったし。あとは……まぁ」
あたしより少し前を歩いていたカーラは振り返る。
「俺にとっても特別な日、だからだよ」
まだ見慣れないカーラの顔が、瞳が、とっても輝いて見えた。
これからの未来はとっても明るいのだ、とでも言うように。
それはたとえ雨雲で遮られたとしても、暗黒の宇宙の中でひっそりと、けれど、確かに輝く一つの星のようだった。
そして、この時は気付かなかったが、後々、その日がカーラの誕生日だったと知る。
なぜ、言い出さなかったのか。
後になって、カーラのことをこっぴどく叱ることになるが、それはまた別のお話だ。
タウ・プピスの少年少女
 Divine
Divine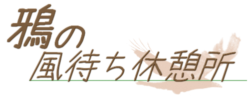
コメント