――夢を見よう。
そっと静かで安らかな優しい夢を。
君と一緒に過ごせるそんな夢を……。
私は、小さな山に住んでいた。
春には暖かな光にうたた寝をし、夏は暑さを凌ぐため川に飛び込んでは遊んでいた。秋になれば赤や黄色に姿を変える木の葉に心を躍らせ、冬は寒さに震えながらも白く染まる景色に手を伸ばす。
そんなたわいもない日々を過ごしていた。
誰にも邪魔されず、誰の邪魔にもならない生活に私は満足していた。ちょっと下りれば、村があるとは知っていたが、踏み入れようとは思わない。
私は人間が嫌いだ。
かつて、一度だけ、村に遊びに行ったことがあったが、彼らは私を見るなり、化け物だと罵っては、武器を向けてきたのだった。以来、あの村には近寄ろうとも思わなくなった。
この山は平和でとても過ごしやすかった。
『やぁ、唯。今日ものんびりお散歩かい?』
よく知った声がいつもと同じく聞き飽きた質問をしてくる。
「やぁ、今日も元気そうだね。蛹のマキ」
私は木に顔を近づけた。案の定、私を呼ぶのは揚羽蝶の蛹マキだ。彼は私と知り合ったその日から、私を見ては同じことを尋ねてくる。
『今日は、何か見つけられそうかい?』
「さてね。なんせ、山奥さ……。そう簡単に変化があったらたまったもんじゃないだろう? それに、私より君の方がそういうのは詳しいだろうに」
『まったくつまらんな。お前さんは。変化に心動かすことがあってもいいだろう』
「その口ぶりだと何かあったみたいだね」
マキは呆れたようにため息をついた。
『今日は珍しいお客だよ。人間だ』
「……人間?」
私の言葉に彼は何も言わず黙り込む。肯定の時、彼が見せる行動だった。それを確認すると駆け出した。山に人間が入ってくるなどあってはならないことだ。変化のない平和が乱されることに私は我慢ならなかった。
「……けて」
山を駆けていた私を止めたのは、小さな人間の声だった。
「たすけて……」
声をたどって見た先には、まだ十にもならないであろう少女の姿があった。少女の体は傷まみれだ。何かあったのであろうことはすぐに分かったが、興味は無かった。それよりも、彼女をここから追い出したかった。けれど、私が動くよりも先に彼女は顔を上げた。丸い漆黒の瞳がこちらを見つめていた。
「き、狐……?」
桜色の唇が震える。私のことを言っているのだろうか。こちらをただじっと見つめながら、彼女はそう言った。
「出てけ」
私は短く、それだけを告げる。少女と話すつもりはなかった。彼女が出ていけば、ここの平和が崩れることはない。
睨みつけたまま私は彼女に繰り返す。出て行ってくれるなら何でもよかった。けれど、彼女は動こうとしない。
「出てけと言ってるのに……」
動かない彼女にしびれを切らした私は、彼女に迫った。
「だから出てけって言ってるだろ!」
私がそう叫ぶより早く、何かが私の頭に触れた。あまりにも急なことに、全身の毛が逆立つ。
「狐さんだぁ!」
はぁ?
きつく体を締め付けられた私はわけもわからず、身をよじる。いったい……どういうことなんだ! 上を見上げれば少女の顔が目の前にあった。どうやら、少女に抱きしめられているらしい状況に私は唖然とする。
「放せって!」
私は何度も大きな声で彼女に訴えるが、彼女は放そうとしない。暴れるのにも疲れたので、じっとしてみると彼女は、やっと私を解放した。
「あ……。痛かった?」
少女はさみしそうにこちらを見つめていた。
「お前、人間だろう?」
強い口調で彼女に問い詰めるが、再び、彼女に体を抱えられてしまう。
「狐さん、一人ぼっちなの?」
どうしてそうなるのか、彼女は勝手に話を進める。
「私もね。一人ぼっちなの。私の家、呪われてるんだって。だから、皆と一緒にいちゃダメなんだって。今日、ちょっと近づいただけだったのに石投げられちゃった。」
そういって、少女は少し泣きそうに笑って痛々しい腕をさすった。私を抱えるのも痛いだろうに、彼女は私を放そうとしなかった。彼女の体温が暖かかった。
少なくとも、この少女にはそんな感情を抱くことはなかった。ちょっと近づいただけで傷つけられたという点ではどこか私たちは似ているような気さえした。たとえ、嫌いな人間であっても、彼女には嫌う要素が一つも見つからなかった。しばらく彼女に抱えられながら、彼女と時間を過ごした。話を聞くうちに追い出そうなどという考えは微塵もなくなっていた。むしろ、私は彼女の私を抱き寄せる手の優しさに、心を許し始めていたのだった。
長く話していたようで、気が付いた時には空はオレンジ色に染まっていた。少女は空を見ると、「また明日も来るから」と私に手を振り、去って行った。
残された私は、呆然とその場で立ち尽くす。
私は、少しして寝床に戻った。そこには、いつものようにマキがいる。
『会ったのかい? 人間に』
「うん……」
私はあいまいに答える。
『何かあったようだな。お前さんがそんな風にはっきりとしないのは珍しい』
「うん。なんか、分からなくなったんだよ。」
私はマキに背を向ける。あまり表情を見られたくなかった。
「そうだ、マキ。狐って知ってる?」
『狐ってのは、人を化かすという、あれか?』
「いや、私に聞かないでくれよ。知らないから聞いたのに」
『あぁ。そうだな……。』
マキも私も眠りについた。
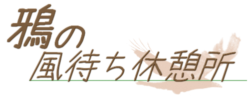

コメント